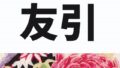「法事の日程、大安でもいいのかな?」
大切な故人を偲ぶ法事。
でも、いざ日程を決めようとすると、「お祝い事のイメージが強い大安に法事をするのは、なんだか気が引ける…」なんて悩んでしまうこと、ありませんか?
カレンダーでおなじみの「六曜(ろくよう)」。
結婚式などのおめでたい行事では「大安吉日!」と喜ばれる一方で、お葬式や法事のような弔事(ちょうじ)では、どう考えたら良いのか迷ってしまいますよね。
ご安心ください!
この記事を読めば、そんなモヤモヤもスッキリ解消。
法事の日取りと六曜の気になる関係から、スムーズな日程決めのコツ、そして知っておきたいマナーまで分かりやすく解説します。
結論:大安の法事、実はまったく問題ありません!
いきなり結論からお伝えしますと、大安に法事を行っても、基本的には何の問題もありません。
「え、本当に?なんだか故人に失礼な気がする…」と思われるかもしれませんね。でも、ちゃんとした理由があるんです。
主に次の2つのポイントを押さえておきましょう。
- 法事の日程は「故人の命日」が最優先だから
- そもそも「六曜」と「仏教の法事」はルーツが別だから
「なるほど、でもそれって具体的にどういうこと?」 そう思われた方のために、これからじっくりご説明しますね。
法事の日程、どう決めるのが正解?~故人を偲ぶ気持ちを大切に~
結婚式のように「縁起の良い日を選んで…」とカレンダーとにらめっこするのとは違い、法事の日程決めには独特の考え方があります。
葬儀:突然の別れに六曜を気にする余裕なし
身内や親しい方との突然の別れ。
そんな悲しみの中で、「仏滅だからお葬式は避けよう」「友引はダメって聞いたけど…」などと六曜を気にしている余裕は、正直なところ、ほとんどありません。
それよりもまず優先されるのは、「火葬場の空き状況」や「斎場の予約が取れる日」。
特に夏場などは、ご遺体の状態を考慮して、できるだけ早く葬儀を行いたいという事情もあります。
多くの場合、故人が亡くなった翌日にお通夜、翌々日に告別式・火葬という流れが一般的です。
法要(四十九日、一周忌など):基本は「命日」、でも柔軟に
四十九日、一周忌、三回忌といった年忌法要は、故人の亡くなった日である「祥月命日(しょうつきめいにち)」に行うのが基本です。
例えば、一周忌なら亡くなってからちょうど1年後の同月同日、ということですね。
ただ、祥月命日が平日にあたると、遠方の親戚や仕事を持つ方が参列しにくい、という問題が出てきます。
そのため、祥月命日よりも前の土日に日程をずらして行うのが一般的です。
大切なポイントは、「後ろ倒しはNG」ということ。
法要の日程を祥月命日より遅らせるのはマナー違反とされていますので、必ず前倒しで調整しましょう。
この際も、「その日がたまたま大安だったから避ける」ということは、ほとんどありません。
「六曜」と「仏教」、実は無関係ってホント?
「でも、『仏滅』って言葉があるくらいだから、仏教と関係があるんじゃないの?」 そう思われるのも無理はありません。
しかし、実は六曜と仏教(つまり法事)には、直接的な関係はないのです。
六曜は、もともと中国から伝わった「暦注(れきちゅう)」と呼ばれる占いの一種。
その日の吉凶を占うもので、一説には賭け事のタイミングを見極めるために使われていたとも言われています。
- 大安(たいあん):
文字通り「大いに安し」。
何事も穏やかに進む、万事において吉とされる日。 - 友引(ともびき):
「凶事に友を引く」という語呂合わせから、葬儀を避ける風習があります。
元々は「勝負なき日」という意味で、良くも悪くもなかったようです。 - 先勝(せんしょう/さきがち):
午前は吉、午後は凶。 - 先負(せんぶ/さきまけ):
午前は凶、午後は吉。 - 赤口(しゃっこう/しゃっく):
正午のみ吉、それ以外は凶。
特に刃物や火の元に注意が必要とされる日。 - 仏滅(ぶつめつ):
元々は「物滅」と書かれ、「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」という意味でしたが、後に「仏も滅するような大凶日」という解釈が広まりました。
このように、六曜はあくまで民間の習慣であり、仏教の教えとは異なるルーツを持っています。
ですから、お釈迦様の教えに基づいて行われる法事の日程を、六曜の吉凶に合わせて組む必要は本来ない、と言われているのです。
じゃあ、法事に「良い日」「悪い日」って本当にあるの?
ここまで読んで、「じゃあ、法事の日取りは何も気にしなくていいんだ!」と思われたかもしれませんね。
基本的にはその通りなのですが、少しだけ注意しておきたい点もあります。
それは、「六曜を気にする方が身内や親戚にいるかもしれない」ということです。
科学的な根拠はないと分かっていても、昔からの慣習を大切にされている方はいらっしゃいます。
ご自身は気にしなくても、周りの方が「大安に法事なんて不謹慎だ」「仏滅は避けるべきだ」と感じてしまう可能性もゼロではありません。
特に気をつけたい「友引」
友引は、「友を冥土へ引き寄せる」という語呂合わせから、葬儀を避ける風習が根強く残っています。
実際に、友引の日を休業日にしている火葬場も少なくありません。
そのため、葬儀だけでなく、法事全般についても友引を避けた方が良いと考える方がいらっしゃいます。
「仏滅」は気にしなくてOK?
六曜の中で最も縁起が悪いとされる仏滅。
しかし、法事に関しては仏教と六曜は無関係なので、仏滅に法事を行っても問題ありません。
ただし、地域によっては「仏滅の法事は避ける」という慣習がある場合も。
念のため、お住まいの地域の風習について年長者や詳しい方に確認しておくと安心です。
お通夜や葬儀の大安は?
お通夜や葬儀も、法事と同様に大安に行っても差し支えありません。
ただ、大安はお祝い事である結婚式の日取りとして選ばれやすいため、万が一、出席予定だった結婚式と葬儀が重なってしまった場合は、一般的に弔事(お通夜や告別式)を優先するとされています。
また、「大安だから今日の葬儀は縁起が良いね」とは、誰も思いませんよね。
むしろ、おめでたい日に葬儀を行うことに抵抗を感じる方もいるかもしれません。このように、大安が良いか悪いかという解釈は、弔事の場面ではあまり意味をなさないのです。
一番大切なのは「思いやり」~周囲への配慮を忘れずに~
法事の日程を決める上で、六曜の吉凶よりもずっと大切なのは、故人を偲ぶ気持ちと、参列してくださる方々への配慮です。
「六曜なんて関係ない!」と自分の考えだけで進めてしまうのではなく、事前に家族や親戚とよく話し合い、みんなが納得できる日を選ぶことが、円滑な法事の準備に繋がります。
特に、年配の方や地域の慣習を重んじる方がいらっしゃる場合は、「大安に法事を考えているんだけど、どう思う?」と、ひと言相談するだけで、お互いに気持ちよく当日を迎えられるはずです。
まとめ:安心して故人を偲ぶために
いかがでしたか?「大安に法事を行っても大丈夫なの?」という疑問は解消されたでしょうか。
結論として、大安に法事を行うこと自体に、宗教的な問題やマナー違反はありません。
しかし、六曜を気にする方がいるのも事実です。
大切なのは、故人を敬う心と、集まる人々への心配り。
この記事が、皆さまの法事の日程決めの不安を少しでも軽くし、心穏やかに故人を偲ぶ時間を持つための一助となれば幸いです。