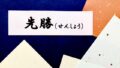法事の日取りを決める時、ふとカレンダーの「大安」や「仏滅」といった文字が気になったことはありませんか?
「お祝い事は大安が良いって言うけど、法事はどうなんだろう?」
「先勝って書いてあるけど、この日に法事をしても失礼にあたらないかな?」
大切な故人を偲ぶ儀式だからこそ、日取りは慎重に選びたいもの。
でも、六曜(ろくよう)まで気にし始めると、一体いつにすれば良いのか分からなくなってしまいますよね。
ご安心ください。
この記事を読めば、六曜のことで悩む必要はなくなります。
法事の日取りに関する迷信と真実、そして何よりも大切にすべきポイントを、誰にでも分かりやすく解説します。
親族トラブルを避け、皆が心穏やかに故人を偲ぶためのヒントがここにあります。
結論:法事と六曜は「無関係」。気にする必要はありません!
まず、一番大切な結論からお伝えします。
仏教の教えと、カレンダーに書かれている六曜は、全く関係ありません。
例えるなら、日本の神社でクリスマスのお祝いをするようなもの。
それぞれ別の文化やルーツを持っているため、本来は結びつけて考える必要がないのです。
- 六曜とは?:
中国で生まれた「占い」が元になっていて、「その日の吉凶」を示したものです。 - 仏教とは?:
インドで生まれ、お釈迦様の教えを説く「宗教」です。
「仏滅」という言葉があるため、仏教と関係が深いように思われがちですが、これは後から当てられた漢字に過ぎません。
ですから、「六曜が悪いから法事ができない」ということは、宗教的には一切ないのです。
では、なぜ「先勝の法事はどうなの?」と気になるの?
本来は無関係とはいえ、やはり気になるのが「先勝」という日の扱いです。
ここもスッキリ解決しておきましょう。
答えは、「先勝の日に法事を行っても、全く問題ありません」。
その理由は2つあります。
- そもそも仏教と無関係だから
先ほどご説明した通り、法事を六曜の吉凶で判断する必要はありません。 - もし六曜を気にする人がいても、「先勝」は縁起の良い日だから
先勝は「先んずれば即ち勝つ」という意味を持つ吉日です。
「何事も急ぐのが良い」とされ、特に午前中は「吉」、午後からは「凶」とされています。
ですから、もし親族の中に六曜を気にする方がいらっしゃったとしても、「先勝の午前中」に法事を行えば、「縁起の良い時間帯だから安心だね」と、むしろ納得してもらいやすいかもしれません。
【要注意】理論より感情?多くの人が気にする「友引」と「大安」
「六曜は気にしなくてOK!」というのが大原則。
しかし、現実は理論だけでは割り切れないもの。
特に、ご年配の方や地域によっては、古くからの慣習を大切にする方もいらっしゃいます。
そこで、トラブルを避けるために知っておきたい、特に注意が必要な日が2つあります。
注意点①:友引(ともびき)
「友を冥土へ引き寄せる」と連想されることから、お葬式の日としてはタブー視されているのが「友引」です。
これは本来の意味ではなく、後から付け加えられた迷信です。
しかし、この考えが社会に広く浸透しているため、今でも多くの火葬場や葬儀会社が「友引」を休業日に設定しています。
迷信と一言で片付けられないほど、社会の慣習として根付いているのが実情です。
法事についても同様に考える方が少なくないため、皆が気持ちよく参列できるよう、「友引」は避けるのが最も無難な選択と言えるでしょう。
注意点②:大安(たいあん)
「何をするにも良い日」とされる大安。
意外に思われるかもしれませんが、この日も法事の日取りとしては注意が必要です。
なぜなら、「故人を偲ぶしめやかな日に、お祝いムード満点の大安を選ぶのは不謹慎だ」と感じる人もいるからです。
良かれと思って選んだ日が、かえって反感を買ってしまう可能性もゼロではありません。
「必ず避けるべき」という訳ではありませんが、「大安だから」という理由だけで日取りを決めるのは少し待って。
親族の考え方も確認してみるのが賢明です。
ちなみに…他の六曜は?(先負・赤口・仏滅)
- 先負(せんぶ):
午前が凶、午後が吉。
「急がば回れ」の日なので、午後からゆったりと法事を行うのに向いているかもしれません。 - 赤口(しゃっこう):
「赤」が火や血を連想させるためお祝い事では嫌われますが、法事では特に問題視されません。 - 仏滅(ぶつめつ):
字面から敬遠されがちですが、「仏様も休む日」と捉えたり、「古いものが終わり、新しく始まる日」として、故人が安らかに旅立つ日とポジティブに解釈する考え方もあります。
【最重要】六曜よりも大切!法事の日取りを決める「基本ルール」
カレンダーの吉凶を気にするよりも、もっと大切にしたい法事の日取りの基本ルールがあります。
それは、「日程をずらすなら、必ず前倒しにする」ということです。
四十九日や一周忌、三回忌といった法事は、本来、故人が亡くなった「命日(祥月命日)」に行うものです。
しかし、平日だと参列者が集まりにくいため、直前の土日などに日程をずらすことがほとんどですよね。
その際に守るべきなのが「前倒しの法則」です。
命日よりも後の日程に変更するのは、故人をお待たせすることになり失礼にあたると考えられています。
これは「故人を大切に想い、偲ぶ気持ち」の表れであり、六曜の吉凶よりもずっと重んじるべき慣習です。
まとめ:最高の法事は「思いやり」から生まれる
法事の日取りと六曜の関係、スッキリご理解いただけたでしょうか。
- 結論として、法事の日取りを六曜で決める必要はありません。
「先勝」も全く問題なし! - ただし、慣習を重んじる方もいるため、「友引」は避けるのが無難です。
- 「大安」も、かえって不謹慎と捉えられる可能性があるので配慮しましょう。
- 六曜よりも、「日程を前倒しにする」という基本ルールを大切にしてください。
最終的に一番大切なのは、六曜の吉凶に振り回されることではなく、故人を偲ぶ気持ちと、参列者への思いやりです。
施主だけで判断せず、家族や主な親族としっかり話し合って日取りを決めること。
それこそが、皆にとって心に残る、最高の法要に繋がるはずです。