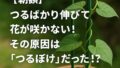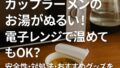こんにちは。
この記事では、生徒会選挙で演説をすることになった方へ向けて、心に残るスピーチを作るためのポイントや例文をご紹介します。
初めての演説で不安を感じている方や、「何を話せばいいの?」と戸惑っている方にも、やさしく丁寧にサポートできる内容を心がけました。
演説は、あなたの思いや考えを周りの人に伝えるチャンスです。
たとえ話すのが得意でなくても、あなたの言葉には力があります。
この記事を読みながら、一緒に構成を考えたり、例文を見て「これならできそう!」と思えるヒントを見つけたりして、自信をつけていきましょう。
少し緊張している方も大丈夫。
あなたのペースで、ゆっくりと読み進めてみてくださいね。
きっと、あなたらしい素敵なスピーチが完成しますよ。
生徒会スピーチで意識すべき5つのキーポイント
聴衆との信頼関係を築こう
演説を聴く人たちに「この人の話をもっと聞いてみたいな」と思ってもらうことがとても大切です。
そのためには、丁寧なあいさつや、聴いている人の気持ちに寄り添った言葉を選ぶことが重要です。
たとえば「みなさんと同じように、私も学校生活をもっと楽しくしたいと思っています」といった共感の表現は、自然と信頼感を生み出します。
また、アイコンタクトや微笑みを交えることで、話す人と聴く人との間にあたたかい雰囲気が生まれます。
具体的な公約を示そう
「学校をもっと良くします!」といった抽象的な言葉だけでは、聴いている人にはイメージが伝わりにくくなってしまいます。
そこで大切なのが、数字や頻度などを取り入れて、より具体的な公約にすることです。
たとえば「毎月1回、図書室の本をリクエストできる制度をつくります」や「体育館の使用ルールをもっとわかりやすく見直します」など、実現可能な内容を意識しましょう。
こうすることで、聴衆の「それならいいかも!」という気持ちを引き出しやすくなります。
情熱を持って語ろう
どんなに内容がしっかりしていても、それを話す人の気持ちがこもっていないと、聴いている人の心に届きにくいものです。
あなたの思いや願いを、自分の言葉でまっすぐに伝えることが、何より大切です。
とくに、語り口や表情、声のトーンに感情をのせてみてください。
たとえば「私は、みんながもっと笑顔になれる学校をつくりたいと思っています」と、目を見て堂々と話すことで、気持ちは自然と伝わります。
問題提起と解決策を明確に伝えよう
スピーチの中で、「今、学校でどんなことに困っているのか」「それをどう変えていきたいのか」をはっきり伝えることで、説得力がぐっと高まります。
たとえば「休み時間の遊び場が限られていて、友達と自由に遊べないことが気になります。
だから私は、中庭をもっと活用できるようにしたいです」といったように、課題→解決策の流れが明確だと、聴く人も納得しやすくなります。
聴衆を巻き込む工夫をしよう
スピーチは一方的に話すだけでなく、聴いている人と気持ちを通わせる場でもあります。
たとえば「みなさんは、今の学校生活にどんなことを感じていますか?」といった問いかけを入れると、自然と心が引き寄せられます。
また、自分の体験談や少し笑える出来事を盛り込むと、会場の雰囲気がやわらぎ、親しみが生まれます。
「みなさんと一緒に、もっと素敵な学校をつくっていきたいです」という呼びかけは、共感を誘う力がありますよ。
印象に残る!スピーチスタイル別の例文集
【王道スタイル】信頼・誠実を重視した定番パターン
まじめで丁寧な言葉づかいで、自分の思いをしっかり伝えるスタイルです。
形式的ではありますが、安定感があり、誰にでも伝わりやすい安心感があります。
「私は、みなさんの声を聞きながら、一歩ずつ進んでいきたいです」といった、誠実で落ち着いた言葉がぴったり。
特に初めて演説をする方におすすめのスタイルです。
【インパクト重視スタイル】冒頭で心を掴む!
「えっ、なにそれ?」と思わせるような驚きの一言や、印象的なエピソードから始めるスタイルです。
たとえば「実は、私は朝の登校で10回転びました。でも、それでも前を向いています!」といった冒頭で、注目を一気に引きつけることができます。
場の空気を動かしたいときや、聴衆に印象を残したい場合に効果的です。
ただし、驚きの要素だけでなく、その後の話の内容とつながっていることが大切です。
【ユーモア交えた面白いスタイル】笑いを誘って印象付ける
クスッと笑えるようなエピソードや例え話を取り入れることで、会場の空気をやわらげ、親しみを持ってもらいやすくなるスタイルです。
たとえば「休み時間に教室でじゃんけん大会をやるなんて、私くらいかもしれませんね!」というような、等身大のエピソードはとても効果的です。
ただし、笑いを取ることが目的ではなく、自分の考えや目標を伝えるための“スパイス”として使う意識を持ちましょう。
【斬新なストーリー展開型】物語で心を動かす
自分の体験や、周囲で起きた出来事をストーリー仕立てで語ることで、感情に訴えるスタイルです。
たとえば「1年生のとき、私は勇気がなくて手を挙げられませんでした。でも、先輩の姿に励まされて、今ここに立っています」といった語りは、共感を呼び、聴く人の心にじんわりと届きます。
物語のように流れがあることで、聴く人も話に引き込まれやすく、最後に「だから私は、今度は誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています」と締めくくることで、感動を残すことができます。
スピーチがすぐ書ける!構成テンプレート3選
スピーチ原稿を一から考えるのは、少しハードルが高く感じるかもしれません。
そんなときは、テンプレートを参考にしてみるととても心強いですよ。
ここでは、タイプの異なる3つの構成パターンをご紹介します。
自分の伝えたい内容や話しやすさに合わせて、しっくりくる型を選んでみてくださいね。
【基本構成テンプレート(初心者向け)】
あいさつ → 自己紹介 → 公約 → 結び。
この順番なら、初めての方でも安心して組み立てられます。
まずは「こんにちは。◯年◯組の◯◯です。」と自己紹介し、どんなことを実現したいのか、簡潔に伝えましょう。
最後は「みなさんと一緒に、よりよい学校にしていきたいと思います。よろしくお願いします。」のように、気持ちよく締めくくるのがポイントです。
構成がシンプルなので、内容に集中しやすく、緊張していても話しやすいスタイルです。
【ストーリー型テンプレート】
悩みや問題 → 自分の経験 → 解決のアイデア → みんなへの呼びかけ。
この構成は、感情を動かしたいときや、共感を得たいときに効果的です。
たとえば「私は、いつも給食の時間に配膳で困っていました」というような、自分の実体験から話を始めると、自然に聴く人の関心を引きます。
そのうえで、「そこで私は、当番表をもっと見やすくしたいと思います」といった解決策を伝えることで、納得感のある流れになります。
「この学校を、もっとみんなにとって優しい場所にしましょう」といった呼びかけで締めくくれば、心に残るスピーチになりますよ。
【問題提起型テンプレート】
「このままでいいのかな?」→「私はこう考えます」→「だからこうしたい」
このスタイルは、少し大人っぽくて、論理的に話したい人におすすめです。
まず「今のルールって、ちょっと使いづらいと思いませんか?」と問いかけることで、聴衆の関心を引きつけます。
そのうえで、「私はもっとみんなが納得できるような決まりごとが必要だと思います」と自分の考えを伝え、具体的な改善策を提案していきます。
最後に「みんなの声を反映できる生徒会にしていきたいです」とまとめることで、説得力のあるスピーチが完成します。
やりがちだけどNG!失敗しやすい演説の例と改善策
ありがちなNG例
- 公約がぼんやりしている
例:「学校を楽しくします!」など、内容が抽象的で実際に何をするのかが見えない - 自慢話が多い
聞いている人は置いてけぼりに…「私はこんなに頑張ってきました!」だけでは共感されにくい - 長すぎる
話が散漫になってしまい、聞き手が途中で飽きてしまう - 難しい言葉や漢字を使いすぎる
小学生や下級生が理解しにくい内容になってしまう - 声が小さい、表情が硬い
せっかくのスピーチも伝わりづらくなってしまう
改善策
- 数字や期間を入れて具体的に!
例:「月に1回、清掃用具のチェックをします」など - 「自分」より「みんな」の視点で考えてみて
みんなにとってどう役立つのかを伝えましょう - 練習でタイムを計りながら、2分以内に収めましょう
余裕を持った構成にするのがコツ - 小学生にも伝わるように、わかりやすい言葉を選ぶ
話す相手を意識した言葉選び - 声は少し大きめに、表情をやわらかくする練習も
第一印象がぐっとよくなります
学年別・役職別の例文ガイド
中学1年生向け:簡潔でシンプルに
中学1年生は、生徒会演説が初めてという方が多いと思います。
そのため、難しい言葉や複雑な構成よりも、自分の気持ちを素直に伝えることを大切にしましょう。
たとえば「私は、まだ入学して間もないですが、この学校がもっと楽しくなるように何かお手伝いがしたいと思いました」といった表現で十分に気持ちは伝わります。
短くても、自分の思いや意欲がきちんと伝わるような言葉を選ぶのがポイントです。
高学年向け:リーダーシップ・経験をアピール
中学2年生・3年生になると、学校生活やクラス活動の経験も増えてくるため、その中で感じたことや取り組んできたことをスピーチに活かしましょう。
たとえば「私は去年、学級委員としてクラスのまとめ役を経験し、みんなの意見を聞きながら行動する大切さを学びました」といったように、自分の行動と気づきを具体的に話すと、リーダーシップが伝わります。
また、下級生の見本になるような姿勢もアピールポイントになりますよ。
会長・副会長・書記などの役職別ポイント
役職によって求められる役割が異なるため、それに合わせた内容を考えることが大切です。
会長の場合は、全体を引っ張るリーダーとしての姿勢や、公平さ・行動力を意識した内容が効果的です。
例:「全校のみなさんが安心して意見を言える、そんな雰囲気を作っていきたいです」
副会長は、会長を支えながら、縁の下の力持ちとして行動できる誠実さをアピールしましょう。例:「サポートに回ることが得意なので、会長と連携しながら行動していきたいです」
書記は記録や情報の整理がメインとなるため、丁寧さや正確さを伝えると好印象です。
例:「みなさんの声を正確に残し、誰もが見やすい資料づくりを心がけます」
それぞれの役割にふさわしい姿勢や行動を言葉にして表すことで、聴く人に「この人に任せたい」と思ってもらいやすくなります。
保護者・先生ができる!スピーチ練習サポートのコツ
子どものアイデアを引き出す質問例
「どうして立候補しようと思ったの?」など、子どもの気持ちに寄り添った問いかけをすることで、自然と本音が引き出されることがあります。
「どんな学校にしたいと思っているの?」「学校で気になることってある?」といったような、テーマを広げる質問も効果的です。
また、「友達からどんなふうに思われたい?」といった視点を変えた質問も、自分の意見を言葉にするきっかけになります。
焦らずゆっくり、子どものペースで話せる環境づくりが大切です。
緊張をやわらげる励ましの言葉
子どもが緊張しているとき、無理に「大丈夫!」と言うよりも、「そのままのあなたで大丈夫だよ」「頑張ってる姿がもう素敵だよ」といった優しい言葉が、心をほぐしてくれます。
「間違えても大丈夫。伝えたいことがあるっていう気持ちが一番大事なんだよ」と伝えるだけでも、子どもの不安は軽くなります。
緊張を否定せず、受け止めてあげることが、安心感につながります。
本番前にできる家庭での練習法
まずは、原稿を声に出して読む練習からスタート。
家族の前で発表したり、録音して自分で聞き直してみたりすることで、話し方や間の取り方がわかってきます。
鏡の前で話すと、表情や姿勢もチェックできて効果的です。
また、実際にスピーチをする時間に合わせて練習してみると、本番のイメージがしやすくなります。
「練習の成果が出たね」「よく頑張ったね」と声をかけることで、自信にもつながります。
時には一緒に笑ったり、少し気分転換をしたりしながら、リラックスした雰囲気で練習できると理想的です。
スピーチ成功のための実践的アドバイス
【ボディランゲージ活用術】
言葉だけではなく、表情や動きも大切な「伝える手段」のひとつです。
身振り手振りをうまく取り入れると、言葉の説得力が増し、聴いている人の印象にも強く残ります。
緊張しているときこそ、体を使って「自信があるように見せる」ことも大切なポイントになります。
信頼のゾーン(中央)
スピーチのときは、できるだけ真正面を見て話すようにしましょう。
目線を下げず、やさしくまっすぐ前を見ることで、聴いている人に誠実な印象を与えます。
手は胸の前で軽く組んだり、自然におろしたりして、落ち着いた雰囲気を心がけましょう。
共感のゾーン(左右)
視線を左右に動かして、教室や会場の隅々に目を向けると「みんなに話しかけている」感じが伝わります。
話すときにうなずいたり、共感の表情を見せたりすることで、より一体感が生まれ、聴く人との距離も近くなります。
アクションのゾーン(前方)
話の要点や力を入れたい部分では、手を軽く前に出したり、ジェスチャーを入れたりするとインパクトが出ます。
たとえば「私はこうしたいんです」と言いながら手を少し前に出すと、熱意がしっかり伝わりますよ。
【実践的な準備のポイント】
スピーチの成功は「準備で決まる」と言っても過言ではありません。
少しずつ準備を積み重ねておくことで、当日は自信を持って話すことができます。
時間管理:2分以内を意識
演説は長ければよいというわけではありません。
短い時間でも「伝えたいこと」を明確にするために、話す内容をあらかじめ整理しておきましょう。
時間を計りながら練習することで、無理なく収めることができます。
原稿作成:話し言葉を意識する
原稿は「書くための文章」ではなく「話すための文章」で作るのがコツです。
難しい言葉や漢字を使うよりも、普段使っているやさしい言葉を選ぶことで、聴いている人に伝わりやすくなります。
「。」ではなく「、」を多めに入れて、息継ぎのタイミングをつかむのもポイントです。
練習方法:録音や家族への発表
自分の声を録音して聞くと、意外と新しい発見があります。
話すスピードや抑揚、聞き取りやすさをチェックしてみましょう。
家族や友達に聞いてもらってフィードバックをもらうのも、より自信につながります。
当日の準備:リラックスと深呼吸
本番当日は、早めに起きて体をほぐし、余裕をもって準備しましょう。
お気に入りの音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりすると、気分もスッキリします。
原稿は何度も見直さずに「やるだけやったから大丈夫」と自分に声をかけて、落ち着いて会場に向かいましょう。
【緊張対策としての呼吸法】
緊張は誰にでもあるもの。
でも、その緊張と上手につき合うことができれば、本番でも落ち着いて話せます。
おすすめなのは「腹式呼吸」。
やり方は簡単。鼻から4秒かけてゆっくり息を吸い、お腹をふくらませます。
そして口から6秒かけてふうっと静かに吐きます。
これを3回ほど繰り返すと、心拍数が落ち着き、気持ちがスーッと整ってきます。
本番前に深呼吸をする時間を少しでも持てるように、早めに行動するのも大切な準備のひとつです。
よくある質問(FAQ)
Q. スピーチで噛んでしまったらどうする?
→ 深呼吸して落ち着いて、もう一度ゆっくり言い直して大丈夫です。
噛んでしまったとしても、それで全てが台無しになるわけではありません。
少し笑顔を見せて「すみません、もう一度言いますね」と自然にリカバリーできれば、逆に親しみやすい印象を与えることもあります。
Q. 公約が思いつかない場合は?
→「自分が学校で不便だと思っていること」を紙に書き出してみましょう。
たとえば「雨の日の傘置き場が少ない」「給食のメニューが分かりづらい」といった小さな気づきも立派なヒントになります。
また、友達と話しながら「こんな風に変わったらいいよね」と意見を交換してみると、新しいアイデアが浮かんでくることもありますよ。
Q. ウケ狙いはやりすぎない方がいい?
→ 笑いも大切ですが、やりすぎは逆効果になることも。
バランスが大事です。
少しのユーモアは緊張をほぐしたり、会場を和ませたりするのに効果的ですが、冗談ばかりになってしまうと「ふざけている」と受け取られてしまうかもしれません。
笑わせることよりも、伝えたい思いをしっかり持っておくことが大切です。
まとめ
生徒会の演説で一番大事なのは、あなたの気持ちが「伝わる」ことです。
上手に話すことや難しい言葉を使うことよりも、心から「こうしたい」という思いを届けることが、聴く人の心に響く鍵になります。
そのためには、共感・具体性・熱意の3つを意識して、自分の言葉で語ることが大切です。
たとえば、自分が日頃感じている学校生活の中の小さな気づきを言葉にしてみたり、友達や先生との何気ないやりとりの中からヒントを見つけたりすることで、よりリアルで説得力のあるスピーチになります。
あなたの経験や想いは、あなただけのもの。
だからこそ、どんな演説よりも心に残る力を持っています。
最後に、どんなに緊張しても大丈夫。準備してきた時間は必ずあなたを支えてくれます。
あなたにしかできない言葉で、聴いている人の心にそっと届く、あたたかくて前向きな演説を目指してみてくださいね。
自分を信じて、堂々とステージに立ってください。心から応援しています!