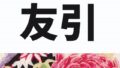「友引に神社へ行っても大丈夫かな?」
「せっかくお参りするなら、縁起の良い日がいいの?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
カレンダーでよく見かける「友引」という言葉。
結婚式などのお祝い事には良い日とされ人気ですが、神社へのお参りとなると、どうなのでしょうか。
もしかしたら、「友を引く」という字面から、何か良くないことを引き寄せてしまうのでは…なんて不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、友引の日に神社へお参りすることを、過度に気にする必要はありません。
でも、せっかくなら気持ちよく参拝したいですよね。
この記事では、そんな気になる友引と神社参拝の関係から、知っておくとちょっと得する六曜の豆知識、さらにはお参りに最適な時間帯や服装のマナーまで、分かりやすく紐解いていきます。
これを読めば、あなたもスッキリした気持ちで神社へ足を運べるはずです!
そもそも「友引」ってどんな日?~六曜のキホン~
まず、私たちの生活に意外と身近な「六曜(ろくよう)」について、簡単におさらいしましょう。
六曜とは、カレンダーに書かれている「大安」「仏滅」「友引」などのこと。
元々は中国から伝わった占いがルーツで、その日の吉凶や運勢を教えてくれる、昔ながらの暮らしの知恵のようなものです。
六曜には以下の6種類があります。
- 大安(たいあん):
何をするにも良いとされる、最強のラッキーデー! - 友引(ともびき):
今回の主役。良くも悪くも「友を引き寄せる」日。 - 先勝(せんしょう/さきがち):
午前は吉、午後は凶。急ぐが吉! - 先負(せんぶ/さきまけ):
午前は凶、午後は吉。慌てず騒がず。 - 赤口(しゃっこう/しゃっく):
お昼どき(午前11時~午後1時頃)のみ吉。
火の元や刃物に注意の日とも。 - 仏滅(ぶつめつ):
六曜の中で最も縁起が良くないとされる日。
さて、この「友引」。
その名の通り「友を引く」という意味合いがあり、お祝い事(慶事)なら幸せをおすそ分けできると考えられ、結婚式の日取りとしては大安に次いで人気です。
一方で、お葬式のような弔事(凶事)では「故人が友を冥土へ引いてしまう」と解釈され、避けられる傾向にあります。
実は、六曜の中での縁起の良さでいうと、友引は大安に次ぐ吉日とされているんです。
「何事も引き分けて勝負がつかない日」という意味もあり、良くも悪くも大きな動きがない、穏やかな日とも言えます。
【本題】友引の神社参拝、実際のところどうなの?
「じゃあ、友引に神社へお参りするのは、やっぱり縁起が良いってこと?」そう思われたかもしれませんね。
これについては、いくつかの側面から見ていきましょう。
-
神社側のスタンス:
「いつでもお越しください」が基本
実は、多くの神社では、六曜そのものをそれほど重視していません。
神道と六曜は、もともと直接的な関わりが薄いためです。
神様は、あなたがどんな日にお参りに来ても、温かく迎えてくださいます。
大切なのは、お参りするあなたの心持ちなのです。 -
信じる気持ちがパワーに:
「友引だから良い日!」もアリ とはいえ、「どうせお参りするなら縁起を担ぎたい!」という方もいらっしゃるでしょう。
もしあなたが「友引は吉日だから、きっと良いことがあるはず!」とポジティブな気持ちでお参りできるなら、それはとても素敵なことです。
その清々しい気持ちが、神様にも通じるかもしれません。 -
あくまで個人の価値観:
気になるなら無理しない
逆に、「友引」という言葉の響きや意味合いがどうしても気になってしまう…というのであれば、無理にその日を選ぶ必要はありません。
大切なのは、あなたが心穏やかにお参りできることです。
もし友引にお参りするなら?気になる「時間帯」の吉凶
「それでもやっぱり友引にお参りしたい!」という方のために、友引の日の時間帯による吉凶について触れておきましょう。
六曜の考え方では、友引の日は時間帯によって運気が変わると言われています。
- 午前中(夜明け~午前11時頃まで):吉
- お昼どき(午前11時頃~午後1時頃まで):凶
- 午後(午後1時頃~日没まで):大吉
このように、友引の日はお昼の時間帯だけが「凶」とされ、それ以外の時間帯、特に午後は「大吉」とされているのです。
ですから、もし友引の日にお参りするなら、お昼どきを避けて、午前中か午後の時間帯、特に午後1時以降に訪れるのが良さそうです。
ただし、これはあくまで六曜上の考え方。
神社参拝の一般的なマナーとしては、また別の視点もあります。
神社参拝、そもそもベストな時間帯ってあるの?
六曜とは別に、神社へお参りするのに適した時間帯というものはあるのでしょうか?
一般的に、神社参拝は「朝」が良いと言われています。
その理由は…
- 清々しい空気に満ちているから:
早朝の境内は、凛とした空気に包まれ、心身ともに清められるような感覚があります。 - 神様へのご挨拶は一日の始まりに:
新しい一日の始まりに神様へご挨拶することで、気持ちよくスタートを切れるでしょう。 - 人が少なく静かにお参りできるから:
落ち着いた環境で、ゆっくりと神様と向き合うことができます。
とはいえ、これも絶対ではありません。
例えば、夕暮れ時は「逢魔が時(おうまがどき)」と言われ、昔から少し特別な時間帯とされています。
物の怪が出やすい時間とも言われ、感受性の強い方は何かを感じるかもしれません。
気になる方は、陽が高いうちの参拝が安心でしょう。
結局のところ、あなたが「お参りしたい」と感じた時が、あなたにとってのベストタイミングと言えるかもしれません。
友引以外にも!神社参拝におすすめの「吉日」いろいろ
「やっぱり縁起の良い日にお参りしたい!」という方のために、友引以外にも神社参拝に向いているとされる吉日をご紹介します。
カレンダーをチェックして、お参りの計画を立ててみてはいかがでしょうか。
- 大安(たいあん):
言わずと知れた最強の吉日。
「大いに安し」という意味で、何をするにも良い日とされています。
神社へのお参りにも、もちろん最適です。 - 神吉日(かみよしにち/じんきちにち):
あまり聞き慣れないかもしれませんが、その名の通り「神事(神様ごと)を行うのに吉」とされる日。
神社への参拝やご祈祷にはうってつけの日です。
意外なことに、この神吉日は1年のうち約半年も巡ってくるんですよ。 - 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび):
「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味の吉日。
何かを始めるのに良い日とされ、お参りをして新たなスタートを切るのにも適しています。 - 天赦日(てんしゃにち/てんしゃび):
「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、暦の上で最上の大吉日と言われています。
年に数回しかない貴重な日です。
これらの吉日が重なる日は、さらに縁起が良いとされています。
逆に、神社参拝を「避けた方がいい日」ってあるの?
基本的には、「この日に神社へ行ってはいけない」という日はありません。
神様はいつでもあなたを待っています。
ただ、六曜の中で「仏滅(ぶつめつ)」や「赤口(しゃっこう)」は一般的に縁起が良くないとされているため、こうした日を意識的に避ける方もいらっしゃいます。
大切なのは、ご自身の気持ちです。
「今日はなんとなく気が進まないな」と感じるのであれば、無理をしてお参りする必要はありません。
あなたが清々しい気持ちでお参りできる日を選びましょう。
【おまけ】神社参拝の服装、これで大丈夫?基本マナー
最後に、神社へお参りする際の服装について少し触れておきましょう。
神様の前に出るのですから、敬意を払った服装を心掛けるのが基本です。
-
普段のお参りなら:
- 厳格な決まりはありません。
Tシャツにジーンズといったカジュアルな服装でも問題ありません。 - ただし、極端に露出の多い服装(タンクトップ、ショートパンツ、ミニスカートなど)や、だらしなく見える服装(ジャージ、スウェットなど)、派手すぎるアクセサリー、作業着などは避けた方が無難です。
- 「清潔感」を第一に、神様に失礼のない、少し襟を正すくらいの気持ちで服装を選ぶと良いでしょう。
帽子やサングラスは、鳥居をくぐる際や神前に立つ際には外すのがマナーです。
- 厳格な決まりはありません。
-
ご祈祷など正式な参拝の場合:
- スーツやワンピースなど、フォーマルに近い服装が求められることがあります。
事前に神社に確認しておくと安心です。
- スーツやワンピースなど、フォーマルに近い服装が求められることがあります。
まとめ:あなたにとって最高の神社参拝を!
友引の日の神社参拝について、長々と語ってきましたが、いかがでしたでしょうか?
結論として、友引の日に神社へお参りすることを、神経質に気にする必要はありません。
六曜はあくまで私たちの暮らしを豊かにするための知恵の一つ。
それよりも大切なのは、あなたがどんな気持ちでお参りするか、です。
「神様に日頃の感謝を伝えたい」
「心を落ち着けたい」
「願いを届けたい」…
そんな純粋な気持ちが生まれた時こそが、あなたにとって一番の参拝日和なのかもしれません。
この記事が、あなたの神社参拝をより心地よく、意義深いものにするための一助となれば幸いです。
どうぞ、清々しい気持ちで、神様とのご縁を結んでくださいね。