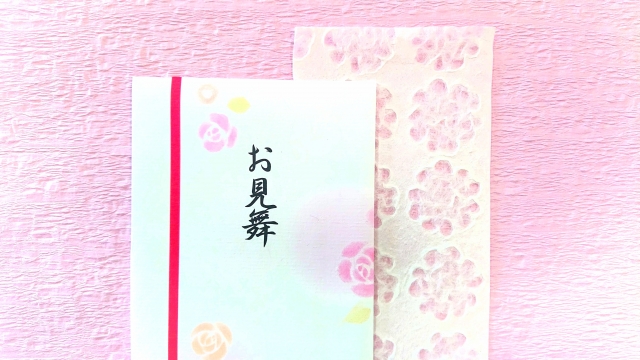大切な人が入院したと聞いたら、一刻も早く駆けつけて励ましたいですよね。
でも、ふと「お見舞いに行く日って、縁起を気にした方がいいのかな?」と悩んでしまうことはありませんか?
特に日本の暮らしに馴染みのある「六曜(ろくよう)」、いわゆる「お日柄」は気になるポイントです。
この記事では、そんなお見舞いの日取りに関する疑問をスッキリ解消!
六曜それぞれの意味から、お見舞いに適した日や時間帯、さらには服装やお見舞い金のマナーまで、あなたが心から相手を思いやる気持ちをスマートに伝えられるよう、分かりやすく解説します。
まずは基本から!お見舞いと「六曜」の関係って?
「そもそも六曜って何?」という方のために、簡単にご紹介しましょう。
六曜とは、カレンダーで「大安」や「仏滅」などと書かれている、その日の吉凶を占うための考え方の一つです。
元々は中国から伝わったもので、日本では結婚式やお葬式など、大切な行事の日取りを決める際によく参考にされます。
お見舞いは冠婚葬祭そのものではありませんが、「相手を気遣う」という大切な場面ですから、日柄を気にする方がいらっしゃるのも自然なことです。
では、それぞれの六曜がどんな意味を持ち、お見舞いとはどんな関係があるのでしょうか?
-
大安(たいあん):
「大いに安し」という意味で、何をするにも良いとされる最高の吉日。
一日を通して吉なので、お見舞いにも最も適していると言えるでしょう。
迷ったら大安を選ぶと安心です。 -
友引(ともびき):
「友を引き寄せる」という意味があります。
お祝い事には良い日とされますが、お葬式は「友を冥土へ引き込む」として避けられます。
お見舞いに関しては、「病に友を引き込む(病気が長引く、悪いことが続く)」と捉えて避けるべきという意見と、「良い方向へ友を引き寄せる」と解釈する向きもあり、意見が分かれる日です。
午前11時~午後1時頃は凶とされます。 -
先勝(せんしょう/さきがち):
「先んずれば即ち勝つ」という意味で、何事も急いで行動するのが良いとされる日。
午前が吉で、午後は凶となります。
お見舞いは午後に伺うことが多いため、少しタイミングが合わせにくいかもしれません。
六曜の中では3番目に縁起が良い日とされています。 -
先負(せんぶ/さきまけ):
「先んずれば即ち負ける」という意味で、先勝とは反対に午前が凶、午後が吉となります。
「負」という字が入っていますが、急がず控えめに行動するのが良い日とされ、六曜の中では4番目に縁起が良い日です。
午後からのお見舞いには比較的向いていると言えるでしょう。 -
仏滅(ぶつめつ):
「仏も滅するような大凶日」と言われ、六曜の中で最も縁起が悪い日です。
一日を通して凶なので、お祝い事はもちろん、お見舞いも避けるのが一般的です。 -
赤口(しゃっこう/しゃっく):
仏滅に次ぐ凶日とされています。
「赤」が血や火事を連想させるため、特にお見舞いのような場面では気にされることが多い日です。
ただし、午前11時頃から午後1時頃(午の刻)のみ「吉」に転じると言われています。
しかし、この時間帯が患者さんの都合に合うとは限りません。
結局、お見舞いに「本当に縁起の良い日」ってあるの?
六曜の意味を知ると、「じゃあ、大安か先負の午後に行けば間違いないの?」と思いがちですが、実はそう単純でもありません。
一番大切なのは、お見舞いされる側の気持ちです。
例えば、一般的に吉日とされる「大安」。
しかし、病気や怪我で大変な思いをしている時に「今日は縁起が良い日だから来ました」と言われても、かえって「不謹慎だ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
また、「友引」も解釈が分かれるため、相手が「友を悪い方へ引く」と考えている場合は避けた方が無難です。
「赤口」や「仏滅」は一般的に凶日ですが、「そんなの全然気にしないよ!」という方もいらっしゃいます。
つまり、お見舞いの日柄の良し悪しは、お見舞いする側が決めるのではなく、お見舞いされる側がどう感じるかが重要になります。
可能であれば、事前にご本人やご家族に「六曜とかって気にするタイプかな?」と、それとなく確認してみるのが最も確実で、思いやりのある方法と言えるでしょう。
お見舞いにベストな「時間帯」は?患者さんの休息を最優先に
日柄も大切ですが、それ以上に気を配りたいのがお見舞いに伺う時間帯です。
一般的に、入院患者さんにとって負担が少なく、お見舞いに適していると言われるのは午後の2時~4時頃です。
その理由は…
- 午前中:
検査や治療、回診などが集中していることが多く、患者さんも病院側も慌ただしい時間帯です。 - お昼前後:
食事の時間と重なってしまいます。 - 夕方以降:
夕食の準備が始まったり、患者さんが休息を取りたい時間帯だったりします。
もちろん、これはあくまで一般的な目安。
病院によって面会時間が細かく決められている場合がほとんどですので、事前に必ず確認しましょう。
そして何より、患者さんのその日の体調を最優先に考えてくださいね。
お見舞いの「日取り」はどう決める?スマートな3ステップ
お見舞いの日取りを決める際は、以下のステップで進めると、相手に負担をかけず、あなたの温かい気持ちがスムーズに伝わります。
-
まずは相手の都合を確認(事前連絡は必須!)
「今日、近くまで来たから寄ってみよう」といった、自分の都合で突然訪問するのは絶対にNGです。
必ず事前に、ご本人かご家族に連絡を取り、お見舞いに行っても良いか、そして都合の良い日時を確認しましょう。 -
候補日をいくつか伝える
相手に「いつがいい?」と丸投げするのではなく、「〇日の午後か、△日の午後なら伺えるんだけど、どうかな?」と、こちらからいくつかの候補日を提案すると、相手も返事をしやすくなります。 -
当日の朝、もう一度連絡を(体調確認の気遣い)
入院中の体調は、日によって大きく変わることがあります。
昨日まで元気そうでも、今日は疲れていたり、気分が優れなかったりすることも。
お見舞いに伺う当日の朝、もう一度「今日、予定通り伺っても大丈夫そうかな?」と連絡を入れ、体調を確認する心遣いを忘れずに。
心遣いが伝わる!知っておきたいお見舞いの基本マナー
お見舞いは、あなたの優しい気持ちを伝える大切な機会。
相手に不快な思いをさせず、心から喜んでもらうために、基本的なマナーをしっかり押さえておきましょう。
- 人数は少なめに:
大人数で押しかけるのは避けましょう。
病室は静養の場です。
多くても2~3人程度にし、同室の他の患者さんへの配慮も忘れずに。 - 声のボリュームは控えめに:
大きな声で話したり、笑ったりするのはNG。
静かなトーンで、穏やかに会話を楽しみましょう。 - 相手が不在・就寝中の場合:
検査などで病室にいない時や、休んでいる時は、無理に待ったり起こしたりせず、静かに退室するのがマナーです。
ナースステーションに「また改めて伺います」と伝言をお願いしましょう。 - 長居は禁物:
患者さんの体力は、あなたが思う以上に消耗しています。
おしゃべりが弾んでも、15分~30分程度で切り上げるのが思いやりです。
「長居してごめんね」ではなく、「早く良くなってね。また顔を見に来るね」と声をかけましょう。 - 会話の内容にも配慮を:
病状を根掘り葉掘り聞いたり、他人の不幸話や心配事を持ち込んだりするのは避けましょう。
相手が話したいことに耳を傾け、明るく前向きになれるような話題を選ぶと良いですね。
お見舞いにふさわしい服装とは?TPOをわきまえた身だしなみ
お見舞いに行く際の服装も、相手への配慮の表れです。
「何を着ていこう?」と迷ったら、以下のポイントを参考にしてください。
- 基本は「清潔感」と「控えめ」:
清潔感のある、派手すぎない服装を心がけましょう。
シワや汚れのない、きちんとした印象のものが良いですね。 - 避けるべき色やスタイル:
- 黒一色の服装: お葬式を連想させてしまうため、避けるのがマナーです。
- 真っ赤な服など、刺激の強い原色や派手な柄物: 目にうるさく感じさせたり、落ち着かない気持ちにさせたりする可能性があります。
- 露出の多い服装(タンクトップ、ミニスカートなど): 病院という場にふさわしくありません。 優しいパステルカラーや、落ち着いた色合いのものがおすすめです。
- 靴選びも大切:
ハイヒールやサンダルなど、コツコツと大きな音がする履物は、他の患者さんの迷惑になることがあります。
静かに歩ける、フラットな靴や音のしにくい靴を選びましょう。 - アクセサリーや香水は控えめに:
大ぶりで華美なアクセサリーや、香りの強い香水・整髪料は、病院では好まれません。
シンプルで清潔感のある身だしなみを心がけましょう。 - 衛生面への配慮:
訪問前に、服にペットの毛やホコリがついていないかチェックするのも忘れずに。
お見舞い金の相場と包み方のマナー
お見舞いとして現金を包む場合、いくらくらいが適切で、どんな点に注意すれば良いのでしょうか。
- 関係性による相場の目安:
- ご両親、兄弟姉妹、祖父母など近しい身内: 5,000円~10,000円程度
- 友人、知人、会社の同僚など: 3,000円~5,000円程度
- 会社関係(上司や取引先など)の場合:
特に注意が必要です。目下の人から目上の方へ現金を贈ることは、失礼にあたるとされる場合があります。
個人的に判断せず、必ず社内の慣例や上司・先輩に相談しましょう。
「〇〇部一同」といった形で、複数人からまとめて贈ることも一般的です。
会社の慶弔規定などを確認するのも良いでしょう。 - 避けるべき金額(忌み数字):
「4(死)」や「9(苦)」を連想させる数字の金額(例:4,000円、9,000円)は避けるのがマナーです。 - お札の選び方と入れ方:
お祝い事では新札を用意するのが一般的ですが、お見舞いの場合は「不幸を予期して準備していた」という意味合いを避けるため、あえて新札ではない、比較的きれいなお札を使うのが伝統的なマナーとされてきました。
しかし、近年ではあまり気にしない方も増えています。
気になる場合は、新札を一度折り目をつけてから入れるか、シワや汚れの少ない古札を選びましょう。
もちろん、破れていたり、ひどく汚れていたりするお札はNGです。
お見舞い用ののし袋(水引が印刷されたものや、紅白の結び切りなど)に入れ、表書きは「御見舞」とします。
まとめ:一番大切なのは、相手を思う温かい心
お見舞いの日柄や時間、服装や持ち物、そして様々なマナー。
覚えることがたくさんあるように感じるかもしれません。
でも、これらはすべて、「相手に余計な気を遣わせず、心から安らぎ、喜んでもらいたい」というあなたの温かい気持ちを形にするためのものです。
六曜などの縁起を気にするかどうかも含め、何よりも大切なのは、患者さんの体調と気持ちを最優先に考えること。
そして、事前の確認と、相手に負担をかけない細やかな心遣いです。
あなたの優しい気持ちが、きっと大切な人の力になるはずです。