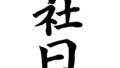夏が近づくと、飲食店の前に並ぶ「土用の丑の日」ののぼりや、スーパーに並ぶうなぎのかば焼きが目に入るようになりますよね。
ニュースでもこの日の様子が取り上げられるほど、季節の風物詩となっているこの「土用の丑の日」ですが、実際のところ、その言葉の由来や意味をご存じでしょうか?
子どもの頃、「どようのうし」と聞いて「土曜日の牛?」と勘違いした経験のある方も多いのではないでしょうか。
大人になって「夏にはうなぎを食べる日」と理解するようになったとしても、「なぜうなぎなのか?」、「そもそも“土用”って何?」といった疑問は意外と知らないままのことが多いものです。
この記事では、そんな「土用の丑の日」について、由来や歴史、風習、なぜうなぎを食べるようになったのか、などの背景をわかりやすくご紹介していきます。
季節の習慣の理解を深めつつ、次の土用の丑の日をより意味のある日にしてみてはいかがでしょうか?
「土用の丑の日」とは?
「土用の丑の日」とは、立春・立夏・立秋・立冬といった「四立(しりゅう)」の直前、約18日間の「土用」と呼ばれる期間のうち、「十二支」で丑(うし)に当たる日を指します。
この考え方は、中国の五行思想に由来しており、万物を「木・火・土・金・水」の五つの要素でとらえる考え方がベースになっています。
それぞれの季節にはこの五行が割り当てられており、春は木、夏は火、秋は金、冬は水。
そしてこれらの季節の移り変わりをつなぐ期間が「土」にあたるとされています。
つまり「土用」とは、次の季節に切り替わる前の準備期間のようなものなのです。
そして「丑の日」は、昔の暦で日を十二支で数える中で「丑」に当たる日を意味します。
つまり「土用の丑の日」とは、季節の変わり目にある18日間のうち、干支が「丑」の日に当たる日のことを指しているのです。
2025年の「土用の丑の日」はいつ?
2025年の夏の土用期間は、7月19日から8月6日まで。
このうち「丑」にあたる日は、7月19日(土)と7月31日(木)の2日間です。
1つの土用期間中に丑の日が2回巡ってくる年もあり、その場合、1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼ぶことがあります。
このように「土用の丑の日」は年によって1回だったり2回だったりするため、事前にチェックしておくとよいでしょう。
ちなみに、春や秋、冬にも土用の丑の日は存在しますが、一般的に「土用の丑の日」と言えば夏のものを指すのが通例です。
なぜ「うなぎ」を食べるの?
では、なぜこの「土用の丑の日」に、うなぎを食べるようになったのでしょうか?
そこには意外な歴史と、当時の知恵が詰まっています。
この風習の始まりとされるのは江戸時代。
あるうなぎ屋が、夏になるとうなぎが全く売れずに困っていたそうです。
そんなとき、知人であった蘭学者・平賀源内に相談したところ、「『本日、丑の日』と書いて店先に掲げてみたらどうか」とのアドバイスを受けました。
当時の人々の間では、「丑の日には“う”のつく食べ物を食べると夏負けしない」という言い伝えがあったことから、「うなぎ」がまさにぴったりだという発想です。
このアイデアは見事に当たり、お店は大繁盛。
それ以来、「丑の日にうなぎを食べる」という習慣が徐々に広まり、現在にまで受け継がれる風習となったのです。
うなぎは本当に夏に食べるべき?
ところで、うなぎの旬をご存じでしょうか?
実は、うなぎの一番おいしい時期は夏ではなく「冬」だと言われています。
秋から冬にかけて、うなぎは産卵のために栄養を蓄え、脂がのってより旨味が増すため、味わいとしては冬のほうが濃厚になるのです。
では、なぜ夏にうなぎを食べることが勧められているのでしょうか?
それは、うなぎに含まれる栄養素が、夏バテ防止に効果的と考えられているからです。
うなぎには、エネルギー代謝を助けるビタミンB1、免疫機能を維持するビタミンA、良質なたんぱく質、さらにはDHAやEPAといった生活習慣病予防にも注目される成分が豊富に含まれています。
また、うなぎは消化吸収にも優れており、暑さで弱った胃腸に負担をかけにくいという点でも、夏にぴったりの食材と言えるでしょう。
実は他にもある!「う」のつく食べ物
うなぎ以外にも、「う」のつく食べ物を食べると良いとされています。
例えば、「うめぼし(梅干し)」「うどん」「うり(瓜)」など。
特に梅干しは殺菌作用や疲労回復効果があるため、古くから夏の健康食品として重宝されてきました。
つまり「丑の日に“う”のつくものを食べて夏を乗り切ろう!」という発想自体が、昔の人の知恵だったわけです。
今も昔も、暑さを乗り越えるための工夫には変わりありませんね。
まとめ
「土用の丑の日」は、古くから続く季節の節目のひとつであり、日本の暦と生活習慣が融合した文化の一例と言えます。
元々は季節の移り変わりを表す「土用」と、日を表す「丑」が組み合わさった暦の概念でしたが、そこに「うなぎ」が結びついたのは、江戸時代の商人の知恵と、時代背景によるものでした。
「うなぎを食べる日」として認識されがちなこの日ですが、その裏には、食文化・健康・信仰・商いといった日本人の暮らしに根ざした様々な要素が詰まっています。
今年の「土用の丑の日」には、ぜひうなぎを味わいながら、その背景にある歴史や知恵にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか?
また、うなぎ以外の“う”のつく食べ物にも注目し、自分なりの「土用の楽しみ方」を見つけてみるのも素敵ですね。