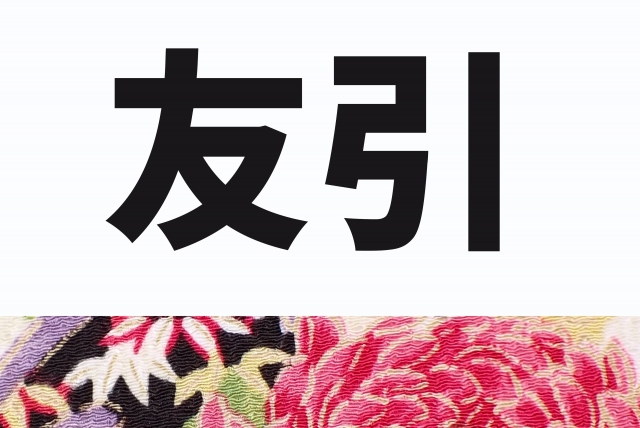「友引にお葬式は避けるべきって聞くけど、お墓参りはどうなんだろう…?」
「お墓参りに行くなら、やっぱり午前中がいいのかな?」
大切なご先祖様へ会いに行くお墓参り。
でも、いざ行こうとすると、ふと「この日でも大丈夫かな?」「時間帯はいつがいいんだろう?」なんて疑問が湧いてくること、ありますよね。
特に「友引」のような日は、お葬式と結びつけて考えられがちなので、お墓参りも避けた方がいいのか迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そんなお墓参りにまつわる「友引」の疑問から、おすすめの時間帯、さらには「お墓参りを避けるべき日」はあるのかまで、気になるポイントを分かりやすく解説します!
これを読めば、スッキリした気持ちでお墓参りに行けるはずですよ。
そもそも「友引」ってどんな日?お墓参りとの関係は?
まず結論からお伝えすると、友引の日にお墓参りをしても全く問題ありません!
「え、でも友引ってお葬式は良くないんじゃ…?」と思った方もいるかもしれませんね。
確かに、「友引にお葬式をすると、故人が友を冥土へ引っ張ってしまう」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。
でも実は、これ、仏教の教えとは全く関係のない、後から広まった俗信(ぞくしん:世間で信じられている迷信のこと)なんです。
もともと「友引」は「共引」と書かれ、「何事も勝負がつかない日」という意味でした。
それがいつの間にか「友を引く」という字面に変わり、「慶事(お祝い事)なら幸せを分け合い、凶事(不幸な出来事)なら不幸を分け合ってしまう」と解釈されるようになったのです。
お葬式に関しては、この「凶事」のイメージから避けられるようになったというわけです。
大切なのは、この「六曜(ろくよう:友引や大安、仏滅など、その日の吉凶を占う考え方)」自体が、仏教や神道とは直接関係がないということ。
お寺さんが「友引にお葬式をしてはいけない」と言い始めたわけではないのです。
お墓参りに関しては、幸いなことに「友引はNG」という俗信は広まらなかったようで、ネット上でもそのような話は見当たりません。
ですから、友引だからといって、お墓参りをためらう必要は全くないのです。
豆知識:友引の時間帯による吉凶って?
ちなみに、友引には時間帯によって吉凶が変わるという考え方もあります。
- 午前中(0時~11時頃):吉
- お昼頃(11時~13時頃):凶
- 午後(13時~24時頃):大吉
もし、どうしても気になる…という方は、お昼の時間帯を避けるのも一つの考え方かもしれません。
でも、先ほどお伝えした通り、友引そのものとお墓参りは関係ないので、基本的には時間帯まで気にする必要はないと言えるでしょう。
「大吉の時間にお墓参りに行ったら何がラッキーなの?」と考えても、ピンとこないですよね。
お墓参り、本当におすすめの時間帯ってあるの?
友引の時間帯は気にしなくても大丈夫として、お墓参りに行くのに「より良い時間帯」というのはあるのでしょうか?
これにはいくつかの考え方があります。
- お盆の場合:
お迎えは早く、お見送りは遅く お盆には、ご先祖様の霊をお迎えし、そしてお送りするという大切な意味があります。そのため、- お迎え(迎え盆):
できるだけ早い時間帯にお墓参りをして、ご先祖様をお迎えするのが良いとされています。 - お見送り(送り盆):
少しでも長く一緒にいたいという気持ちを込めて、少し遅めの時間帯が良いとされることもあります。
- お迎え(迎え盆):
- お彼岸の場合:
特に決まりはなし 春と秋のお彼岸には、お盆のような時間帯に関する特別な考え方はあまりないようです。 - 午前中が推奨される理由:
「ながら参り」を避けるため 「お墓参りは、他の用事を済ませた後でついでに行く『ながら参り』は良くない」という考え方があります。
ご先祖様に敬意を表し、まず一番に会いに行くという意味で、午前中が良いとされることがあります。
これは、清々しい気持ちでご先祖様と向き合えるというメリットもありそうですね。
これは守ろう!避けるべき時間帯
推奨される時間帯はいくつかありますが、逆に避けるべき時間帯は比較的はっきりしています。
- 日没後や夜間など、暗くなった時間帯
- 霊園や墓地の開園時間外
これらは必ず守りましょう。
特に夜間のお墓参りは、足元が見えにくく、段差などで転倒する危険性が高まります。
地域によっては「お墓で転ぶと縁起が悪い」という言い伝えもあるようです。
安全のためにも、明るい時間帯にお参りするようにしましょう。
お墓参り、いつ行くのがベスト?
お墓参りに行くタイミングとして、多くの方が思い浮かべるのは以下の時期ではないでしょうか。
- お盆:
一般的には8月13日~16日頃(地域によっては7月15日近辺)。
特にお迎えの意味を込めて、13日の午前中が良いとされることが多いです。 - お彼岸:
春分の日(3月20日か21日頃)と秋分の日(9月22日か23日頃)を中心に、前後3日間を含めた各1週間。 - 命日:
故人の亡くなった日や、親しい方の命日。 - 年末年始:
新年のご挨拶や、一年の感謝を伝えに。 - 思い立った時:
実は、お墓参りに行く時期に「この日はダメ!」というタブーは基本的にありません。
「ご先祖様に会いに行きたいな」「ちょっと報告したいことがあるな」と思った時が、一番良いタイミングと言えるでしょう。
逆にお墓参りを避けた方がいい日ってあるの?
いろいろ調べてみましたが、「この日にお墓参りに行ってはいけない」という特定の日付は見当たりませんでした。
お盆やお彼岸といった「お墓参りをする風習がある日」の情報はたくさんありますが、NGとされる日は基本的にないと考えて良いでしょう。
ですから、ご家族や友人と都合が合う日に、気持ちよくお参りに行くのが一番です。
ただし、雨の日など天候が悪い日は、足元が悪く滑りやすいことがあります。
特に古いお墓や整備されていない場所では危険も伴うため、無理はしない方が賢明です。
安全第一で、お天気の良い日を選びましょう。
まとめ:大切なのは「気持ち」。でも地域の風習もチェック!
さて、友引とお墓参りの関係について、長々とご説明してきましたが、一番大切なポイントをもう一度。
- 友引(六曜)とお墓参りは、仏教的な観点からは全く関係ありません。
- お墓参りに行ってはいけない日も、基本的にはありません。
ですから、「友引だから…」と気にしすぎる必要はありませんし、お仕事やご自身の都合に合わせて、行ける時にお参りすれば大丈夫です。
ただ、お墓参りの時間帯については、「午前中が良い」「お盆のお迎えは早く」といった昔からの考え方や風習が残っている地域もあります。
ご自身の住んでいる地域や、ご親族の間で「うちはこうしているよ」という慣習があるかもしれません。
そういった地域の風習には「これが絶対の正解!」というものはありませんが、周囲の方々と気持ちよくお付き合いするためにも、一度確認してみるのも良いかもしれませんね。
何よりも大切なのは、ご先祖様を敬い、感謝する気持ちです。
形式にとらわれすぎず、心を込めてお参りすることができれば、きっとご先祖様も喜んでくれるはずですよ。