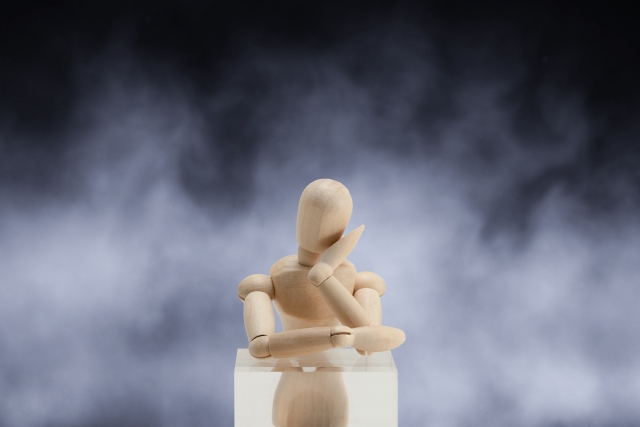大切なご家族を失った悲しみは、計り知れないほど深いものです。
しかし、その悲しみに浸る間もなく、お通夜、お葬式と、故人を見送るための準備を慌ただしく進めなければなりません。
そんな中、ふと手に取ったカレンダーの「大安」という文字が目に留まり、手が止まってしまった…そんな経験をされる方は少なくありません。
結婚式などのお祝い事でこそ喜ばれる「お日柄の良い日」。
そんな日に、悲しみの儀式であるお葬式を執り行うのは、故人やご先祖様に対して失礼にあたるのではないか、縁起が悪いのではないか…と、不安が心をよぎるのも無理はないでしょう。
この記事では、そんなお葬式の日取りに関するあらゆる疑問や不安を、一つひとつ丁寧に解きほぐしていきます。
最初に結論をお伝えします。
大安にお葬式を行うことは、全く問題ありません。
そして、本当に注意すべき日は別にあります。
その理由を深く掘り下げながら、分かりやすく解説していきます。
その前に…そもそも「六曜(お日柄)」って何?
日取りの話をする前に、基本となる「六曜(ろくよう)」について簡単にご説明します。
六曜とは、カレンダーに書かれている「大安」や「仏滅」などのことで、元々は中国で時刻の吉凶を占うために使われていた考え方です。
日本に伝わってから、次第にその日の吉凶を示すものへと変化しました。
よく「お日柄」と言われるのは、この六曜のことを指します。
代表的な6種類とその意味を見てみましょう。
- 大安(たいあん):
「大いに安し」の意味。
万事において吉とされる、六曜の中で最も縁起の良い日。 - 友引(ともびき):
良くも悪くもない「引き分けの日」。
後述しますが、お葬式では特別な意味を持ちます。 - 先勝(せんしょう/さきがち):
午前中は吉、午後は凶。
急ぐことが良いとされる日。 - 先負(せんぶ/さきまけ):
午前中は凶、午後は吉。
何事も控えめにするのが良い日。 - 赤口(しゃっこう/しゃっく):
正午ごろ(午前11時~午後1時)のみ吉で、他は凶。
特に火や刃物に注意すべき日。 - 仏滅(ぶつめつ):
「物が滅する」日。
万事に凶とされ、お祝い事は避けられる傾向があります。
ここで最も重要なのは、これらはあくまで古くからの占いの一種であり、仏教の教えとは一切関係がないということです。
これを踏まえて、大安の葬儀について見ていきましょう。
やはり結論は「問題なし」。大安のお葬式をポジティブに捉える視点
前述の通り、六曜と仏教は無関係ですので、大安にお葬式を執り行っても全く問題ありません。
それどころか、視点を変えれば、大安を「故人を安らかに見送るのにふさわしい日」と捉えることもできます。
- 「大いに安し」の日:
故人が安らかに旅立てる、と考えることができます。 - 「万事においてスムーズに進む日」:
葬儀という大切な儀式が、滞りなく無事に執り行われる日、と解釈することも可能です。
実際に、故人が亡くなった日から順にお通夜、告別式と日程を組んだ結果がたまたま大安だった、というのはごく自然なことです。
由来の異なる占いに気を揉む必要はありませんので、どうぞご安心ください。
ただし、一番大切なのは「周りの人との心の調和」
理論上は問題なくても、少しだけ配慮したいのが、ご親族や参列者の気持ちです。
六曜を生活の指針として大切にされている方、特にご年配の世代には、「縁起の良い大安にお葬式なんて…」と、心情的に抵抗を感じる方がいらっしゃるのも事実です。
葬儀で最も大切なのは、故人を偲ぶ人々が心を一つにし、穏やかな気持ちで見送ること。
ささいな日取りの問題で親族間にわだかまりが生まれてしまっては、故人も悲しむでしょう。
もし、お日柄を気にする方がいらっしゃることが分かっているなら、事前に優しく声をかけてみるのが最善です。
<相談の会話例>
「おばあちゃん、お葬式の日が大安になってしまったの。
でも、お寺様に確認したら、仏教とは関係ないから大丈夫だと言われていて。
むしろ『故人が安らかに旅立てる穏やかな日』という意味にもなるみたい。
みんなで気持ちよく見送ってあげたいのだけど、どう思う?」
このように、一方的に「問題ない」と伝えるのではなく、相手の価値観を尊重しつつ、相談という形で丁寧に対話することが、円満な解決への鍵となります。
要注意!本当に避けるべきは「友引」です
大安よりもずっと注意が必要な日。
それが「友引」です。
元々、友引は「勝負なき日」とされ、勝敗のつかない引き分けの日という意味でした。
ところが、時代と共に「留引」「共引」と字が変わり、やがて「友引」という字が当てられました。
そこから「(亡くなった人が)友を(あの世へ)引いていく」という連想が生まれ、お葬式を執り行うのは縁起が悪い、と強く避けられるようになったのです。
この慣習は迷信ではありますが、日本社会に深く根付いています。
その結果、現在では全国のほとんどの火葬場が、友引を休業日として定めています。
つまり、「縁起が悪いから」という気持ちの問題以上に、「火葬場が休みで、物理的に火葬ができない」という極めて現実的な理由から、友引の葬儀は行われないのです。
これは、日程を決める上で避けては通れない最重要ポイントです。
「仏滅」のお葬式は?よくある誤解
「仏が滅する」という字面から、仏教と関係が深く、お葬式にはかえって良いのでは?
あるいは、縁起が悪すぎてダメなのでは?
と誤解されがちなのが「仏滅」です。
これも全くの誤解です。
「仏滅」の「仏」は当て字で、元々は「物滅」と書きました。
すべての物が滅び、新しく始まる日、という意味合いだったのです。
こちらも仏教とは一切関係ありませんので、お葬式を執り行うことに何の問題もありません。
まとめ:形式よりも、心をこめて故人を見送るために
目まぐるしく進む葬儀の準備の中で、日取りは悩ましい問題の一つです。
最後に、大切なポイントをもう一度整理します。
- 大安・仏滅のお葬式
全く問題ありません。
六曜と仏教は無関係なので、気にする必要はありません。 - 配慮すべきこと
ご親族など、周りに六曜を気にする方がいる場合は、事前に優しく対話し、皆が納得できる形を選びましょう。 - 絶対に避けるべき日
「友引」です。
縁起の問題だけでなく、ほとんどの火葬場が休業しているため、物理的に葬儀ができません。
お葬式の日取りで最も大切なのは、形式にこだわりすぎることではなく、ご遺族や親しい人々が心から故人を偲び、「ありがとう」の気持ちを伝える時間を持つことです。
どうか、根拠のない占いに心を悩ませすぎず、故人との最後のお別れの時間を、大切にお過ごしください。