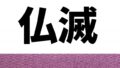「最近なんだかツイていない…もしかして厄年?」
「厄払いって行ったほうがいいのかな」
「でも、お日柄が悪い日しか行けないし…」
人生の節目に訪れる厄年を前に、漠然とした不安やたくさんの疑問が頭をよぎる方は少なくないでしょう。
特に、スケジュール帳とにらめっこして、ようやく空いていた日が「赤口(しゃっこう)」だった時の、あの何とも言えない気持ち。よく分かります。
でも、ご安心ください。
結論から言うと、赤口の日に厄払いを行っても全く問題ありません!
この記事では、なぜ赤口でも大丈夫なのかという理由をさらに深く掘り下げ、それでも気になる方のために縁起の良い時間帯、最適な日取りの決め方から、当日のマナーまで、あなたの不安をスッキリ解消する情報を余すところなくお届けします。
読み終える頃には、きっと晴れやかな気持ちで厄払いに向かえるはずです。
なぜ赤口でもOK?知っておきたい「厄払い」と「お日柄」の本当の関係
「でも、お祝い事は大安が良いって言うし…」と思いますよね。
その考え方、間違いではありません。
しかし、厄払いの場合は少し事情が違うのです。
それには、ちゃんとした理由があります。
厄払いは「お祝い」ではなく心身の「デトックス」だから
結婚式や地鎮祭といったお祝い事は、これからの未来が素晴らしいものになるよう願いを込めて、縁起の良い日を選びます。
一方で、厄払いは「知らず知らずのうちに溜まった厄(やく)を神様のお力で祓い清め、心身をリセットする」ための儀式。
例えるなら、体の調子を整えるための定期検診や、パソコンの動作を軽くするためのデータ整理のようなものです。
「おめでとう!」という祝祭ではなく、「これでスッキリ!」という浄化のイメージですね。
だからこそ、お祝い事ほど厳密にお日柄にこだわる必要はない、とされているのです。
「六曜」と「神社」は、実はルーツが全くの別モノ
大安や赤口といったお日柄は「六曜(ろくよう)」と呼ばれる、中国で生まれた占いが元になっています。
それが日本に伝わり、江戸時代以降に民間で広く使われるようになりました。
- 六曜の簡単な意味
- 先勝(せんしょう): 午前は吉、午後は凶。急ぐが吉。
- 友引(ともびき): 朝晩は吉、昼は凶。「友を引く」とされる。
- 先負(せんぶ): 午前は凶、午後は吉。勝負事は避けるのが無難。
- 仏滅(ぶつめつ): 一日を通して大凶とされる日。
- 大安(たいあん): 一日を通して大吉とされる日。
- 赤口(しゃっこう): 昼(午前11時~午後1時)のみ吉。火や刃物に注意。
一方、私たちが厄払いをお願いする神社は、日本古来の「神道(しんとう)」にもとづく場所。
その歴史は六曜よりもずっと古く、考え方のルーツが異なります。
例えるなら、海外の有名なレストランの予約をするのに、日本の「大安」を気にする人がいないのと同じ感覚です。
文化のバックグラウンドが違うのですね。
実際に多くの神社では、「六曜は関係ありませんので、ご都合のよい日にお越しください」と案内されることがほとんど。
神様は、カレンダーの吉凶ではなく、あなたの「お参りしたい」という真摯な気持ちを何よりも大切にしてくださるのです。
それでも気になる!赤口の「ゴールデンタイム」を賢く狙おう
理由を聞いて納得はしたけれど、「せっかくなら、少しでも縁起の良いタイミングを選びたい!」と思うのが人情ですよね。
その気持ち、とてもよく分かりますし、素晴らしい心がけです。
ご安心ください!
赤口は一日中ずっと縁起が悪い日、というわけではありません。
実は、午前11時頃から午後1時頃までの「午の刻(うまのこく)」だけは、凶が転じて「吉」になるゴールデンタイムが存在するんです。
厄払いの所要時間は、神社の規模や混雑状況にもよりますが、15分~30分ほどが一般的。
この「吉」の時間帯にご祈祷が終わるように予約すれば、たとえ赤口の日でも、心から晴れやかな気持ちで神様にご挨拶できますよ。
【予約のワンポイントアドバイス】
電話で予約する際に「赤口の日なのですが、午前11時から午後1時の間でお願いできますか?」と直接相談してみるのが確実です。
WEB予約の場合は、備考欄に希望時間を添えてみるのも良いでしょう。
そもそも厄払いはいつ行くのがベスト?時期とタイミングを解説
厄払いの日取りに厳格なルールはありませんが、いくつかの一般的な目安があります。
時期:なぜ「節分まで」と言われるの?
昔から「年が明けてから、節分(2月3日頃)まで」に行うのが良い、と言われることが多いです。
これは、旧暦では「立春」が新年の始まりとされていたため。
その前日である「節分」は、今でいう大晦日のようなものでした。
季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えられていたため、「古い年の厄を払い、新しい気持ちで新年を迎える」という意味を込めて、この時期に厄払いをする風習が根付いたのです。
もちろん、これはあくまで古くからの習わし。
節分を過ぎてしまっても、ご利益が減るなんてことは全くありません。
誕生日や年の初めなど、ご自身の区切りが良いタイミングで大丈夫です。
厄年:前厄・本厄・後厄、いつ行く?
厄年は、本厄の年を挟んで前後の前厄・後厄と、3年間にわたって続くとされています。
- 前厄: 厄の兆候が現れ始める年
- 本厄: 最も災いが起こりやすいとされる年
- 後厄: 厄の力が薄らいでいく年
どの年にお祓いを受けるかは、地域や神社、個人の考え方によりますが、最も重要な本厄には必ず行く方が多いようです。
より丁寧に考えるなら、3年間毎年お祓いを受けるか、前厄の年にお祓いを受けて「3年間の無事」をまとめて祈願するのも良いでしょう。
【当日の準備】服装・持ち物・初穂料のマナー
いざ厄払い当日。何を着て、何を持っていけば良いのでしょうか?
基本的なマナーを知っておけば、当日慌てずに済みます。
- 服装:
神様の前に出るのですから、敬意を表す服装が望ましいです。
スーツやワンピースが理想ですが、なければ襟付きのシャツやジャケット、きれいめのカジュアル(ジーンズやサンダルは避ける)でも問題ありません。
大切なのは「清潔感」です。 - 持ち物:
基本的には手ぶらで大丈夫ですが、神社によっては予約票などが必要な場合も。 - 初穂料(はつほりょう):
ご祈祷に対するお礼として神社にお納めするお金です。
相場は5,000円~10,000円ほど。
のし袋(紅白蝶結びの水引)に入れ、表書きは「御初穂料」または「玉串料」、下に自分の名前をフルネームで書きましょう。
【番外編】どうせなら最高の日に!吉日カレンダー&避けたい日
「やっぱり日取りには徹底的にこだわりたい!」という方のために、厄払いにぴったりの吉日と、気になるなら避けておきたい日をご紹介します。
厄払いにおすすめ!強力な吉日ベスト3
- 大安(たいあん):
言わずと知れた最強の吉日。
「何事においても吉」とされ、終日いつでも縁起が良いので安心です。
人気が集中するため、早めの予約が吉。 - 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび):
「一粒のもみが万倍にも実る」という、何かを始めるのに最適な日。
厄払いで得た清々しい気持ちやご利益が、万倍にもなって返ってくるかもしれませんね。 - 天赦日(てんしゃにち):
「天がすべての罪を赦(ゆる)す」とされる、暦の上で最上の大吉日。
年に5~6回しか訪れない貴重な日で、心身をリセットする厄払いにはまさに最適な日と言えるでしょう。
気になるなら避けておきたい日
- 仏滅(ぶつめつ):
六曜の中で最も縁起が悪いとされる日。 - 不成就日(ふじょうじゅび):
「何事も成就しない」とされる日。
せっかくの厄払いも「成就しない」と考えると、少し気持ちが晴れないかもしれません。 - 十方暮(じっぽうぐれ):
「十方(あらゆる方角)が塞がれ、途方に暮れる」という意味合いがあり、物事が上手くいかないとされる期間です。
一番大切なのは「あなたと家族」が納得すること
最後に、これまでのどんな情報よりも大切なことをお伝えします。
それは、ご家族への配慮です。
自分自身は「お日柄なんて気にしない!」と割り切れても、ご両親や祖父母の世代は「縁起の悪い日に大切な子どもの厄払いだなんて…」と、心から心配されるかもしれません。
厄払いは、あなた自身のためだけではなく、あなたを大切に思う家族の安心にも繋がる、とても温かい儀式です。
「今度厄払いに行こうと思うんだけど、この日は赤口なんだ。でも神社は六曜と関係ないみたいだし、お昼の良い時間に行こうと思うんだけど、どう思う?」 そんな風に、ひと言相談を持ちかけてみてください。
その優しい心遣いが、何よりの「吉」を呼び込むはずです。
まとめ:あなたらしい日を選んで、晴れやかに厄を払おう!
厄払いの日取り選びについて、たくさんの疑問や不安が、期待や安心に変わったでしょうか。
- 赤口の厄払いは全く問題なし!文化が違うから大丈夫。
- 気になるなら午前11時~午後1時のゴールデンタイムを狙おう。
- 当日は清潔感のある服装と、感謝の気持ち(初穂料)を忘れずに。
- 何より大切なのは、あなた自身と、あなたの家族が心から納得すること。
厄払いは、決して怖いものでも、面倒なものでもありません。
あなたの人生の新たな一歩を応援し、背中をそっと押してくれる、とてもポジティブな儀式です。
あなたにぴったりの日を見つけて、心身ともにスッキリと、晴れやかな一年をスタートさせてくださいね。