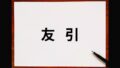結婚式は「大安」、お葬式は「友引」を避ける…。
宝くじを買うならやっぱり「大安」?
カレンダーにひっそりと書かれている「六曜(ろくよう)」。
私たちは日々の暮らしの中で、知らず知らずのうちにこの6つの言葉を意識しています。
しかし、
「どうして大安は良い日なの?」
「仏滅ってそんなに悪いの?」
と聞かれると、意外と答えられないものですよね。
また、カレンダーをよく見ると「大安の次が赤口じゃない!」なんて、順番が飛んでいることに気づいたことはありませんか?
この記事では、そんな六曜の基本から、歴史的背景、カレンダーで順番が飛ぶ不思議な法則、そして現代における賢い付き合い方まで、あらゆる角度から徹底解説します。
読み終わる頃には、あなたも誰かに教えたくなる「六曜プチ専門家」になっているはずです!
そもそも「六曜」って何もの?意外と知らないその正体
まずは六曜の正体から探っていきましょう。
ミステリアスな響きですが、その歴史を知ると非常に興味深いものです。
六曜は「ろくよう」または「りくよう」と読み、その起源は中国にあります。
一説には、三国時代の名軍師・諸葛亮(しょかつりょう)が軍略を立てるために用いたという伝説まであるほど(真偽は定かではありませんが、ロマンがありますね)。
これが鎌倉時代から室町時代にかけて日本に伝わり、江戸時代に庶民の間に爆発的に広まりました。
当時、暦の出版がブームになり、人々は暦に書かれた運勢を今日の私たちがおみくじや星占いを楽しむように、生活の指針としていたのです。
面白いのは、もともと「その日の吉凶」ではなく、「時間を区切って吉凶を占う」ものだったということ。
日本に伝わってから、その解釈が独自に変化し、現在のような「一日の運勢」を示す形になったのです。
「仏滅」は仏教と関係なし!政府に禁止された過去も
「仏滅」という字面から、仏教と深い関わりがあると思われがちですが、これは全くの無関係です。
むしろ、浄土真宗の開祖である親鸞は「日の吉凶に惑わされるのはよくない行いである」と説いたほどで、仏教界では六曜を迷信と捉える考え方が主流です。
さらに明治時代には、近代化を目指す政府が「根拠のない迷信は文明国家にふさわしくない」として、カレンダーへの六曜記載を禁止した歴史もあります。
それでも六曜が消えなかったのは、それだけ庶民の生活に深く、強く根付いていた証拠と言えるでしょう。
六曜6兄弟!それぞれのキャラクターと攻略法を徹底解剖
六曜には6つの種類があります。
それぞれどんな意味があり、どのように付き合えば良いのか。
個性豊かなキャラクターと、その日の「おすすめアクション」を見ていきましょう!
大安(たいあん):最強の吉日、でも元々は…?
【特徴】
六曜界の絶対的エース。
何をするにも良いとされるパーフェクトな日。
【本来の意味】
「大いに安し」の意で、「特に害のない、穏やかな日」。
大成功が約束されるというよりは、「トラブルなく物事を進められる日」というのが本来のニュアンスです。
【おすすめアクション】
- お祝い事:
結婚、入籍、結納、お宮参りなど - 新しいこと:
開業、開店、引っ越し、納車、財布の新調 - その他:
宝くじの購入、願い事
友引(ともびき):幸せも不幸せも「友を引く」日
【特徴】
「友を引く」という字の通り、良くも悪くも周りを巻き込む日。
【本来の意味】
もとは「共引」と書き、「勝負がつかない引き分けの日」でした。
【おすすめアクション】
- やってOK:
幸せのおすそ分けとして、結婚式やパーティー、お祝い品の発送に最適。大安の次に人気の日取りです。
- 避けるべきこと:
お葬式、お通夜、お見舞い。「友を冥界へ引いてしまう」と考えられ、現在も多くの火葬場が友引を休業日としています。
先勝(せんしょう/さきがち):「午前中」が勝負のスピードスター
【特徴】
「先んずれば即ち勝つ」という意味を持つ、スピーディーさが吉を呼ぶ日。
【攻略法】
午前中は吉、午後からは凶。
とにかく午前中が勝負です。
【おすすめアクション】
- 午前中に:
契約、訴訟、願い事、急ぎの用事、大切なプレゼン - 午後は:
なるべく静かに過ごし、大きな決断は避けるのが無難。
先負(せんぷ/さきまけ):急がば回れの「午後」からが本番
【特徴】
先勝とは真逆で、「先んずれば即ち負ける」。
慌てず、騒がずが吉。
【攻略法】
午前中は凶、午後からは吉に転じます。
【おすすめアクション】
- 午後に:
急がない契約、話し合い、ゆっくり始めたい用事。 - 午前中は:
準備の時間にあて、勝負事は避けるのが賢明。「負」という字を気にしすぎず、午後から落ち着いて行動しましょう。
赤口(しゃっこう/しゃっく):お祝い事は要注意な「厄日」
【特徴】
「赤」という字が火や血、死を連想させるため、万事に凶とされる日。
特に、火事や刃物、怪我に注意すべきとされています。
【攻略法】
唯一、お昼の時間帯(午の刻=午前11時頃~午後1時頃)だけは吉。
【おすすめアクション】
- やってOK:
どうしても用事を済ませたいなら、お昼休みを狙うのが手。 - 避けるべきこと:
祝い事全般(結婚、入籍など)、契約、納車、お見舞い。
仏滅(ぶつめつ):最凶の厄日?いや、「最強のリセットデー」です!
【特徴】
「仏も滅するほどの大凶日」という、何とも不名誉なレッテルを貼られた日。
【本来の意味】
元々は「物滅」と書き、「一度すべてが滅び、物事がリセットされる日」でした。
【おすすめアクション】
- リセット&スタート:
悪縁を断ち切る、引っ越し(古い環境をリセット)、大掃除、不要品の処分。何かを新しく始めるには最適という考え方もできます。
- お葬式や法事:
仏教と無関係なので、仏滅に行っても全く問題ありません。
カレンダーの謎!六曜の順番が飛ぶのはなぜ?
さて、いよいよこの記事最大の謎解きです。
六曜の基本的な並びは「先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口」の繰り返し。
しかし、カレンダーではこのサイクルが急に断ち切られ、順番が飛ぶことがあります。
その理由は、私たちが今使っている「新暦(太陽暦)」と、六曜が生まれた頃の「旧暦(太陰暦)」という、2種類のカレンダーが混在していることにあります。
- 旧暦(太陰暦):
月の満ち欠けが基準。
1ヶ月が約29.5日で、1年が約354日。 - 新暦(太陽暦):
地球が太陽の周りを回る周期が基準。
1年が約365日。
ご覧の通り、1年で約11日のズレが生じます。
このズレを解消するため、旧暦には「閏月(うるうづき)」という13ヶ月目のある年が存在します。
六曜には、この旧暦に基づいた「旧暦の各月1日の六曜は、固定されている」という絶対的なルールがあるのです。
- 旧暦1月1日・7月1日 → 先勝
- 旧暦2月1日・8月1日 → 友引
- 旧暦3月1日・9月1日 → 先負
- 旧暦4月1日・10月1日 → 仏滅
- 旧暦5月1日・11月1日 → 大安
- 旧暦6月1日・12月1日 → 赤口
この古いルールを今のカレンダーに当てはめているため、カレンダーの途中で「旧暦の月」が変わる(旧暦の朔日=ついたちが来る)タイミングで、六曜の並びも強制的にその月の固定六曜にリセットされるのです。
これが、順番が飛ぶ現象の正体です。
六曜との上手な付き合い方 〜迷信と片付けない、現代の活用術〜
ここまで読んで、「結局、六曜って信じるべき?」と思われたかもしれません。
結論から言えば、「便利なツールとして、上手に活用するのが正解」です。
- ゲン担ぎとして楽しむ:
「今日は大安だから、きっとうまくいく!」と自分の背中を押すポジティブな材料にする。 - 行動のきっかけにする:
「先勝だから、面倒なタスクを午前中に片付けよう」と、一日の計画を立てるリズムメーカーとして使う。 - 相手への「配慮」として使う:
自分は気にしなくても、取引先や年配の方は気にされるかもしれません。契約日やお祝いを渡す日取りを考える際に六曜を意識するのは、立派なコミュニケーション術です。
六曜は、あなたを縛るルールではありません。
最終的な決断は、あなた自身が下すものです。
ですが、古くから日本人の暮らしに寄り添ってきたこの文化を、日々の生活をちょっと豊かに、そして面白くするためのスパイスとして、賢く取り入れてみてはいかがでしょうか。