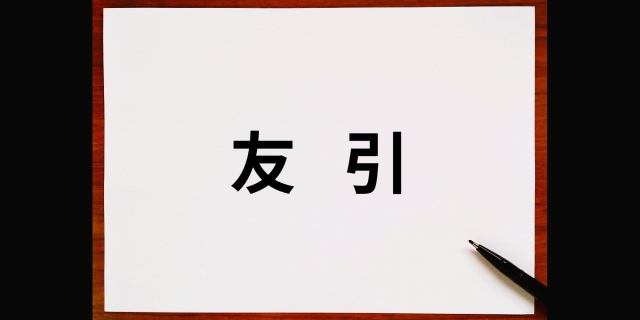「結婚式の日取り、大安は予約でいっぱい…」
「やっと決まった引っ越し日。でも親から『友引だから、お昼は避けなさいね』と言われて…友引って一体どういう日なの?」
カレンダーにひっそりと書かれている「大安」や「仏滅」といった言葉たち。
これらは「六曜(ろくよう)」と呼ばれ、私たちの生活に古くから根付いています。
普段は気にしなくても、結婚式や入籍、引っ越しといった人生の大切なイベントでは、やっぱり縁起の良い日を選びたいものですよね。
そんな時、必ず選択肢にあがるのが「友引(ともびき)」です。
しかし、「友を引く」という字面から、「お祝い事に使っていいの?」「何か不吉な意味があるんじゃない?」と、その扱いに迷ってしまう方が非常に多いのも事実です。
ご安心ください。
友引は、その特性を正しく理解すれば、大安にも劣らない幸運を呼び込むことができる、非常に使い勝手の良い吉日なのです。
この記事では、「友引」の本当の意味から、お祝い事や弔事での具体的な付き合い方、そして「こんな時はどうする?」という細かな疑問まで、あなたの不安をスッキリ解消できるよう、徹底的に解説していきます!
結論:友引は「お昼以外のお祝い事」に最強の味方!
まず、この記事の結論からお伝えします。
友引は、結婚式や引っ越しといったお祝い事には、大安に次いで縁起の良い日です。
ただし、友引を使いこなすためには、絶対に覚えておきたい2つの鉄則があります。
- お昼の時間帯(午前11時~午後1時)は「凶」:
この2時間だけは運気が下がる「魔の時間」とされています。
何かを新しく始めるのは避けましょう。 - お葬式は厳禁:
「友を(冥土へ)引く」という解釈から、お葬式を行うのは古くからのタブーとされています。
この2点さえしっかり押さえれば、友引はあなたの計画の強い味方になってくれます。
では、具体的なシーン別に、その活用法をじっくり見ていきましょう。
【慶事編】友引は「幸せの連鎖」を生む特別な日
「友を引く」という言葉は、お祝いの場面では「幸せを友に引き寄せる」「幸福の輪が広がる」という、ポジティブで非常に縁起の良い意味に変わります。
結婚式・入籍:最高の「幸せのおすそ分け」をしよう!
人生最大のハレの日である結婚式。
友引を選ぶカップルは年々増えています。
- 知っておきたいメリット:
- 予約の取りやすさとコスト:
「結婚式といえば大安」という根強い人気から、大安の日は半年前、人気の式場では1年以上前から予約が埋まることも。その点、友引は大安に次ぐ吉日でありながら、比較的予約が取りやすい傾向にあります。
式場によっては「友引割引」のようなお得なプランを用意していることもあり、賢くコストを抑えたいカップルには狙い目です。
- ゲストへの祝福を込めて:
あなたの結婚を心から祝ってくれる大切な友人たち。「この幸せが、みんなにも連鎖しますように」という願いを込めるのに、友引はこれ以上ないほどピッタリの日です。
二次会の招待状などに「幸せのおすそ分けができますように、友引の日を選びました」と一言添えるのも、素敵な演出ですね。
- 予約の取りやすさとコスト:
- プランナーへの相談ポイント:
- 挙式や披露宴の開始時間を、必ず11時~13時の間から外して予約しましょう。
「午前10時半スタート」「午後1時半スタート」などが理想です。
午前中に始まった式がお昼の時間帯にまたがるのは問題ありません。
- 挙式や披露宴の開始時間を、必ず11時~13時の間から外して予約しましょう。
- 入籍日としての友引:
- 大安の日に役所へ行くと、同じように考えるカップルで窓口が混雑することも。
その点、友引は比較的スムーズに手続きできる可能性が高いです。
- 最強の入籍日を作りたい方へ:
さらに縁起を担ぎたいなら、「天赦日(てんしゃにち)」や「一粒万倍日(いちりゅう まんばいび)」と友引が重なる日を探すのがおすすめです。これらは六曜とは別の吉日で、カレンダーで確認できます。
友引の「幸せの連鎖」パワーに、他の吉日のエネルギーが加わった日は、最高のスタートを切れるでしょう。
- 大安の日に役所へ行くと、同じように考えるカップルで窓口が混雑することも。
引っ越し・納車・七五三:新しい門出を幸運で満たす
人生の新たなスタートを切るイベントでも、友引は心強い味方です。
- 引っ越し:
「良いご近所さんや、素晴らしい人間関係を引き寄せる」とされ、新生活のスタートに最適です。引っ越し業者も日取りによる料金変動があるため、大安を避けて友引を選ぶことで、費用を抑えられる可能性があります。
作業開始時間をお昼からずらすように依頼しましょう。
- 納車:
友引の本来の意味は「引き分け」。つまり「良くも悪くもない平穏な日」ということから、「事故などを起こさず、穏やかなカーライフを送れる」と解釈され、納車日として人気です。
一部で「友を轢く」と連想する人もいますが、これは本来の意味ではないので、気にする必要はないでしょう。
- 七五三:
大安の神社は大変混み合います。特に小さなお子様連れの場合、人混みは避けたいもの。
友引を選べば、少し落ち着いてお子様の成長をお祝いできるはずです。
ご祈祷の時間は、神社に確認して、お昼時を避けて予約するのがスマートです。
【弔事編】友引とのお付き合いで、最も注意すべきこと
お祝い事では吉日となる友引ですが、お悔やみ事ではその意味が180度反転します。
これは、自分だけでなく周囲の人々への配慮として、必ず知っておくべき知識です。
お葬式は、なぜ絶対に避けるべきなのか
友引の日にお葬式を行わないのは、日本の古くからの慣習です。その理由は2つあります。
- 縁起上の理由:
「友を冥土へと引いていってしまう」という解釈が一般に広く浸透しています。たとえ遺族が気にしなくても、参列する親戚や知人の中には強く気にする方がいるかもしれません。
無用なトラブルや、大切な人を亡くした悲しみの中でさらに心を痛める事態を避けるためにも、友引の葬儀は避けるのが賢明です。
- 物理的な理由:
この風習に基づき、多くの火葬場や斎場が友引を定休日としています。つまり、そもそも予約が取れないのです。
近年は営業する施設も増えましたが、それでも数は限られます。
「友人形」という風習
万が一、どうしても友引に葬儀をせざるを得ない場合、一部の地域では「友人形(ともびきにんぎょう)」と呼ばれる人形を棺に入れ、「友の代わりにこの人形を連れて行ってください」という厄払いの風習が残っています。
しかし、これはあくまで例外的な慣習です。
お通夜は行っても良いが…
「お葬式がダメなら、お通夜も?」と思いがちですが、お通夜は友引に行っても差し支えないとされています。
お通夜は故人との別れを惜しむ場であり、告別の儀式である葬儀とは意味合いが異なると考えられているためです。
ただし、注意点が一つ。
友引の翌日は「友引明け」と呼ばれ、一日待っていた葬儀が殺到します。
そのため、火葬場が非常に混雑し、希望の時間に予約が取れない、あるいは順番待ちが長くなる可能性があります。
この混雑を見越して、結果的にお通夜も友引を避ける、という判断がなされることも少なくありません。
そもそも「友引」って何?六曜の仲間たちと本当の意味
ここで、友引のルーツと、その仲間である「六曜」について少し詳しく見てみましょう。
これを知ると、日取り選びがもっと面白くなりますよ。
もともと、友引は「留連(りゅうれん)」という字で、意味は「勝負なき日=引き分けの日」。
良くも悪くもない、ただ平穏な日でした。
それが時代と共に「共引」となり、いつしか陰陽道の「友引日(ともびきび)」という考えと混ざって、現在の「友引」という字と「友を引く」という意味に変化したのです。
六曜には、友引の他に以下の5つの仲間がいます。
- 大安(たいあん):
「大いに安し」の意味。
一日中すべてにおいて吉とされる最強の吉日。 - 先勝(せんしょう/さきがち):
「先んずれば即ち勝つ」。
午前中が吉、午後は凶。 - 先負(せんぶ/さきまけ):
「先んずれば即ち負ける」。
午前中が凶、午後は吉。 - 赤口(しゃっこう/しゃっく):
午の刻(11時~13時頃)のみ吉で、他は凶。
特に火や刃物に注意すべき日。 - 仏滅(ぶつめつ):
「物が滅する日」。
一日中すべてにおいて凶とされる大凶日。
こうして見ると、友引の「お昼だけ凶」という特徴がユニークであることがわかりますね。
ちなみに、これらの六曜は中国発祥の占いが元であり、仏教や神道とは直接の関係はありません。
明治時代には政府が「迷信である」として一度使用を禁止したほどです。
しかし、人々の生活に深く根付いていたため、今も文化として残っています。
【友引なんでもQ&A】こんな時どうする?
- Q. 宝くじを買うのはどう?
- A. 問題ありません。
「友を引き寄せる」という意味で、金運を仲間内に広げるイメージで買うのも楽しいかもしれません。
- A. 問題ありません。
- Q. 契約や商談は?
- A. 「引き分け」という意味から、勝ち負けをはっきりさせたい商談には不向きという考え方もあります。
しかし、お昼の時間を避ければ大きな問題はありません。
むしろ、相手と良好な関係を築きたい場合は吉とされます。
- A. 「引き分け」という意味から、勝ち負けをはっきりさせたい商談には不向きという考え方もあります。
- Q. お見舞いは行ってもいい?
- A. 「友を病気に引き込む」と連想されかねないため、気にされる方もいます。
避けるのが無難ですが、もし行く場合は相手の気持ちを最優先に考えましょう。
- A. 「友を病気に引き込む」と連想されかねないため、気にされる方もいます。
まとめ:友引は、人間関係を豊かにする「コミュニケーションツール」
最後に、友引との上手な付き合い方を改めてまとめます。
- お祝い事:
大安が取れない時の「第二候補」ではなく、「幸せの輪を広げる」という積極的な意味を持つ吉日として活用しましょう。 - お悔やみ事:
故人と参列者への配慮から、お葬式は必ず避けるのがマナーです。 - 絶対ルール:
何をするにもお昼の11時~13時は避ける!
六曜は、単なる迷信と片付けることもできます。
しかし、相手への配慮を示したり、物事を始めるきっかけにしたりと、私たちの生活や人間関係を円滑にするための「知恵」や「コミュニケーションツール」として捉えてみてはいかがでしょうか。
友引の意味を正しく理解し、あなたの人生の大切な一日を、より豊かで素晴らしいものにしてくださいね。