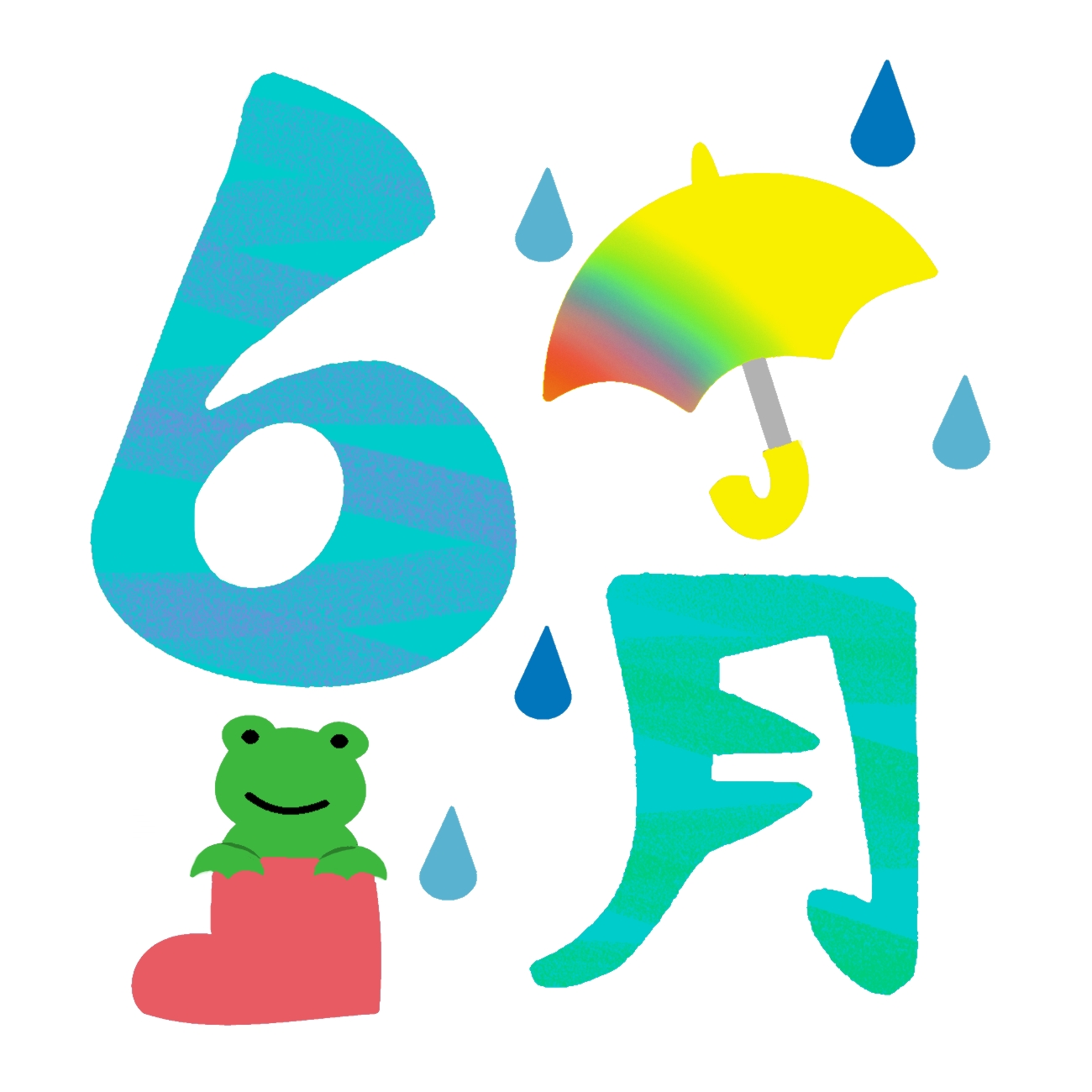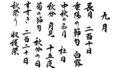「梅雨入り」と「入梅」、どちらも雨の季節を示す言葉ですが、実は意味や使われ方が異なります。
例えば、カレンダーに「入梅」と書かれているけれど、天気予報では「梅雨入りまだ」と言われて混乱した経験はありませんか?
この二つの違いを理解しておくと、季節の変わり目がより明確に感じられるようになりますよ。
この記事では、それぞれの言葉が持つ意味や背景、そして実生活への関わりをわかりやすく解説します。
それでは、一緒に見ていきましょう。
「入梅」と「梅雨入り」の違いとは?
「入梅」って何?
「入梅(にゅうばい)」は、雑節と呼ばれる暦上の節目のひとつで、梅雨が始まる目安とされてきた日です。
現在では、太陽の動きに基づいて「太陽黄経が80度に達する日」が入梅とされています。
昔の日本では、入梅を目安に農作業の段取りを考えていた時代もありました。
また、「梅の実が熟し始める時期」とも重なるため、この時期の雨は“恵みの雨”として受け止められていたのです。
ただし、実際の天気とは必ずしも一致しないため、今では気象庁が発表する「梅雨入り」の方が、実際の気象を示す目安として重視されています。
ちなみに、節分や彼岸と同じく「入梅」も雑節に含まれます。
これらはいずれも、季節の移ろいを感じ取るための暦の工夫なんですね。
「梅雨(つゆ)」って?
梅雨は、日本特有の雨の多い季節で、初夏から夏の初めにかけて続きます。
空は曇天が続き、しとしとと雨が降りやすい時期です。
「梅雨」という字には、「梅の季節に降る雨」という意味があります。
この季節は梅の実がちょうど熟す頃でもあり、昔の人々はその自然の流れと共に季節を感じていたのですね。
一方で、「黴雨(ばいう)」という表記もあります。こちらは「かびの雨」とも読めるように、湿度が高く、カビが発生しやすい季節でもあることを指しています。
ちなみに「梅雨」を「つゆ」と読むのは、「露(つゆ)」から来ているとも言われています。
雨がもたらす潤いは、植物や農作物にとって欠かせない恩恵でもあるのです。
この季節の始まりを指す言葉として「栗花落(ついり)」という言い回しもあります。
栗の花が散る頃に雨の季節が始まるという、自然に寄り添った感覚が表れていて素敵ですね。
「入梅」と「梅雨入り」の決定方法の違い
たとえば、6月10日がカレンダーで「入梅」となっていても、必ずしもその日から雨が続くとは限りません。
一方、「梅雨入り」は気象庁が観測データをもとに発表するもので、実際の天気に即したものです。
入梅は毎年決まった日に訪れますが、梅雨入りはその年の気候状況によって日付が前後します。
| 項目 | 入梅 | 梅雨入り |
| 判断基準 | 太陽の動き(太陽黄経)に基づく | 気象の実際の状況に基づく |
| 発表者 | 暦の専門家 | 気象庁 |
| 信頼性 | 日付が固定されている | 実際の気象パターンに基づき高い |
| 天気傾向 | 必ずしも雨とは限らない | 雨や曇天が続く見込みがある時に発表 |
このように、「入梅」と「梅雨入り」は似たような言葉に見えても、目的も基準も大きく違うのです。
2025年の入梅は?
2025年の入梅日は、6月11日(水)です。
この日を境に、おおよそ1か月間は雨が多くなる時期に入ります。
「入梅」の語源を探る
「入梅」という表現には、いくつかの由来があります。
ひとつは中国の暦の影響です。
中国でも、梅の実が実る時期の雨を「梅雨」と呼んでいたため、それが日本にも伝わったという説があります。
もう一つの由来は、少し文学的です。
湿気が増えるこの季節には「黴(かび)」が生えやすくなりますが、「黴雨(ばいう)」という表現は響きが悪いため、「梅」の字に置き換えられたとも言われています。
日本文化では、ネガティブなものを美しい表現に変えて受け入れる習慣があります。
この発想も、季節と共にある暮らしの知恵ですね。
季節を味わう「入梅いわし」
雨の季節になると、美味しくなる食材も登場します。
そのひとつが「入梅いわし」と呼ばれるマイワシです。
この時期のマイワシは産卵前で脂がたっぷり。旨みが強く、刺身でいただくのが最高です。
特に、鮮度の良いものを三枚におろして生姜や大葉とともに食べると、その濃厚な風味が楽しめます。
栄養価も高く、EPAやDHAなどの不飽和脂肪酸、ビタミンD、カルシウムなどを多く含んでいます。
梅雨で気分が沈みがちな時期こそ、旬の味覚で気持ちを明るくしたいですね。
「入梅の候」ってどう使うの?
「入梅の候(にゅうばいのこう)」は、6月の時候の挨拶として使われる言葉です。
ビジネス文書や丁寧な手紙の冒頭で使われ、季節の変わり目を意識した表現として活躍します。
例文:
・拝啓 入梅の候、貴社益々ご発展のこととお慶び申し上げます。
・拝啓 入梅の候、皆様方におかれましてはご健勝のことと存じます。
ただし、北海道では梅雨がほとんどないため、「入梅の候」は避けるのが無難です。
その代わりに「初夏の候」「長雨の候」などが適しています。
なお、「入梅の候」が使える時期には明確な終わりはありませんが、一般的には6月上旬から中旬あたりが目安とされています。
まとめ
「入梅」は暦上の季節の目安、「梅雨入り」は実際の気象を示す指標。
両者は似て非なるものですが、どちらも日本の自然と深く結びついています。
この季節ならではの行事や味覚、言葉に触れながら、雨の季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。